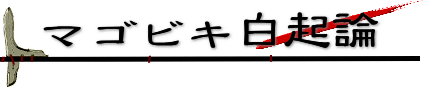
(6)抗命事件と白起の最期
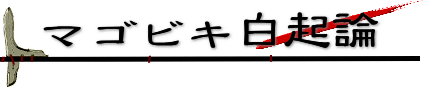
(6)抗命事件と白起の最期
 白起は悲運の武将であったともいえる。
白起は悲運の武将であったともいえる。
白起は史記によると昭王51年11月に死んだ。
白起の最期を語るには、白起が趙に大勝した長平の戦いの直後に遡ろうと思う。
長平の戦いの後、白起にさらなる武勲をあげさせ、立場が逆になることを恐れた范雎は
白起の邯鄲攻めに待ったをかける。
この様子を史記・白起列伝に見てみよう。
■「史記(Ⅱ)」(徳間書店)
48年(紀元前259年)10月、秦はふたたび上党郡を平定し、その後、軍を二手に分け、王コツの軍は皮牢を攻略し、司馬梗の軍は太原を平定した。
韓・趙は秦の勢いを恐れ、弁舌の士蘇代に手厚い贈物をもたせ、秦の宰相応侯を説得した。
蘇代は言った。
「趙括をとらえたのは、武安君(白起)でしたな」
「いかにも」
「まもなく、趙の国都邯鄲を包囲するつもりでしょう」
「いかにも」
「これで、趙が滅びれば、秦王が天子となり、武安君は三公になりますな。
あの人が攻めおとした城邑は、七十余にものぼり、南はエン・郢・漢中を平定し、北は趙括の大軍を壊滅させました。
かの周公旦・召公セキ・太公望呂尚の功績もこれにはおよびません。
ですから、趙が滅び、秦王が天子になるようなことになれば、武安君はまず三公に昇進することは確実です。
そうするとあなたは、不本意ながら武安君の下で働くことになりますが、その期に及んで不服を唱えてみたところでどうしようもありますまい。
先年、貴国が韓を攻めて、ケイ丘を包囲し、上党を苦境におとしいれた際、上党の民衆は趙へ逃亡しました。
これでおわかりのように、天下の民は秦に帰属することを嫌っております。
いま趙を滅ぼしたとしても、その領民は、北に住む者は燕へ、東に住む者は斉へ、南に住む者は韓・魏へそれぞれ避難してしまい、秦が実際に獲得支配できる人口は、いくらにもなりますまい。
ひとまず韓・趙の和議を受け入れ、これ以上、武安君に手柄をたてさせないほうが...」
そこで応侯は秦王に言上した。
「わが軍は疲労しております。
韓・趙の和議を受け入れて、軍を休息させてはいかがかと存じます」
王は応侯の意見を従い、韓から垣雍、趙から六つの城邑を割譲させることで和議を結び、正月、全軍に引き揚げを命じた。
白起はこれを聞いて、応侯に対し反感を抱くようになった。
このとき、秦が軍を撤収しなければ、歴史は変わっていたかもしれない。
一年後、結局秦はまた邯鄲を攻めようとするが、今度は白起が待ったをかける。
戦いには機があり、一年前はまさに邯鄲を落すチャンスだった、今はもう無理だと白起はいう。
昭襄王は白起の意見をはねつけ、邯鄲を攻めるが一向に落ちない。
白起なら落せるのではと、白起に軍を率いるよう命じるが、白起は病気と称して行こうとしない。
范雎にも頭を下げさせ、懇願するが白起は動かない。
そのうえ、白起は「わたしの意見をきかなったが、いまのありさまはどうか」と批判してるというから
王は腹をたて、白起の身分を剥奪し、流刑にする。
ぐずぐずして咸陽を出ようとしない白起に、王は追い討ちをかけ自害を命じる。
剣を首にあて白起はつぶやく。
「わたしは天にどのような罪を犯して、このようなことになってしまったのか」
しばらくしてまた言った。
「わたしはもともと死ぬべきであったのだ。
長平の戦いで降服してきた趙兵数十万を騙して生き埋めにした。
これは十分死に値する。」
そうして自殺した。
彼の死は無罪によるものだった。
秦人はこれを憐れんで、白起をあちこちの村で祭ったという。
この、抗命事件のくだりは戦国策に比較的長く記載されている。
■「戦国策」(徳間書店・中国の思想Ⅱ)
―秦と趙との間で戦国時代最大といわれる「長平の戦い」がおこったのは、前260年のこと。大勝した秦の損害も甚だしく、追いうちをかける余裕はなかった。そして、1年たった。
秦の昭王は、人民を休養させ、兵力も回復したので、もう一度趙を討とうとした。
名将・武安君が諌めた。
「それはなりません」
昭王は言った。
「昨年は不作で人民が飢えていた。それにもかかわらず、おまえは、この際、徹底的に趙を攻めたいから軍糧をふやしてくれ、と要求したではないか。
あれから1年、人民を休養させ、人材を育成した。
食糧も蓄えた。将兵の手当も倍増してやった。それなのに『ならぬ』とはいかなるわけか」
「長平の戦いでは、わが方は大勝、敵は大敗しました。
秦は勝利にわき立ち、戦死者は鄭重に埋葬されました。
負傷者はあつい看護を受けました。弱った者には栄養が与えられました。
しかしそのために秦の財力は底をついたのです。
それに反し、敗れた趙では、戦死者は収容されず、負傷者は手当も受けられぬ窮状でありました。
しかし、国中悲しみを分け合い、憂いを共にして耕作につとめ、こうして国力を蓄えました。
たとい、昨年の倍の軍勢をさし向けたとしても、おそらく趙の守りは昨年の十倍も固いでありましょう。
趙は長平で敗れて以来、臣下はもちろん、王までが、早朝から夜ふけまで政務に励んでいます。
近隣の諸国にも、鄭重に使節を派遣し、燕・魏と結び、斉・楚とよしみを通じ、ひたすら秦に備えてきました。
いまや趙の国力は充実し、近隣との外交も円満です。
趙を討つ時機ではありません。」
「もう軍を動員したのだ。やめるわけにはいかぬ」
昭王は将軍の王陵に命じて趙を討たせた。王陵は苦戦に陥って五つの軍団を失った。
昭王は武安君を派遣しようとしたが、武安君は病気を口実に辞退した。
昭王は武安君のもとに応侯(范雎)をつかわした。
「楚は領地五千里、兵力百万の大国。
だが、先年、あなたはわずか数万の兵を率いて攻め入り、エン・郢を陥れて廟を焼き払い、さらに東の竟陵まで進撃した。
楚の者どもは、ふるえあがって逃げるばかり、あえて立ち向かってくる者がなかった。
また韓・魏と戦ったときは、相手は同盟して大軍を動員したのに、あなたの兵力はその半分以下だった。
それでもあなたは伊闕で二カ国の大軍をうち破り、流血に大盾がただよい、二十四万人も殺すほどの大勝利をおさめた。
それ以降、韓・魏は今日まで鳴りをひそめている。
それがあなたの功績だということは、誰知らぬ者もない。
いまや趙は長平の戦いで兵力の七、八割を失い、国力が弱まっている。こんどわが国が動員した兵力は、趙軍の数倍もある。
王は、あなたを大将に任命して、ぜひとも趙をやっつけたい、といわれる。
かつて少数の兵力であざやかに大軍を破られたあなたのこと、強力な軍を率いて弱敵にあたるなら、わけもないはずだ。」
武安君は答えた。
「あの時は、楚王は大国を鼻にかけて政治をかえりみなかった。
臣下同士も、手柄をたてた者がかえってねたまれ、へつらい上手が幅をきかせて忠臣が退けられた。
人民にも見放され、城も荒れほうだい、忠臣もなく、守りも弱かった。
そこでわたしは、敵地深く侵入し、橋をこわし船を焼いて味方の戦意をかきたて、村を略奪して軍糧を確保した。
味方の兵は、軍営をわが家とし、大将を父母のごとく慕った。
一致協力して事にあたり、死んでも退却しなかった。
一方、楚の兵は、自国の領内で戦ったので、家のことばかり心配して浮き足立ち、闘志がなかった。
だから勝てたのです。
また伊闕の戦いでは、孤立した韓は、魏ばかりあてにして自国の兵を投入したがらない。
魏は魏で、韓の精鋭をあてにし、それを先陣にたてようとする。
互いに利害が一致しなかった。
そこで、韓の陣地を襲うとみせかけ、全軍一丸となって魏軍の不意をついた。
魏軍を破ったからには韓軍はものの数ではない。
勝ちに乗じて追撃した。
だからこの時も勝てたのです。
いずれも、形勢を十分に計算した。
勝つのは当然で何の不思議もない。
ところが昨年、長平で趙の軍を破ったときは、深追いをさけて、全滅させる好機を失った。
その結果、趙は、耕作にはげんで蓄積を増やした。
孤児を養い幼児を育てて人口をふやした。
武器を整備して兵力を増強した。
城をつくり、堀を深くして守りを固めた。
国王は家臣に、家臣は勇士に、それぞれ礼をつくしている。
平原君の一族郎党のごときは、妻や妾に兵卒の服のほころびまでつくろわせている。
いまの趙は、越の勾践が会稽山で和を請うたときと同じこと。
一致協力して国力の増強につとめている。
いま攻めても、趙の守りは固い。
戦いを挑んでも応じない。
都を包囲しても、勝てない。
城を攻めても、落ちない。
村を略奪しても、得るものはない。
出兵するからには、勝たねばならない。
さもないと諸侯は秦を軽んじて、趙に援軍を送るにちがいない。
いま攻めても、得なことはひとつもない。
それに、病中のわたしには出陣もおぼつかぬ」
応侯は赤面して引き退り、その旨を王に言上した。
「よし、白起がいやだというなら、おれがやる」
昭王は、さらに兵力を増強し、王陵にかえて王コツ(秦の武将)を大将に任命して趙を討たせた。
王コツは八、九カ月も邯鄲を囲んだが、死傷者ばかり出して、攻略できなかった。
かえって趙のゲリラに後方を攪乱され、しばしば敗れるありさまだった。
武安君は、
「だから言わないことではない」
昭王は腹を立てた。
武安君のもとを訪れ、無理やり病床から起こし、
「病中ではあろうが、寝ながらでもよいから指揮をとれ。
殊勲をたてれば重賞を与える。
拒むなら、このままではすまさんぞ」
武安君は平伏した。
「命をきけば、手柄をたてなくとも罪を免れ、拒めば、罪を犯さなくとも誅を受けます。
それを承知しながら申し上げるのですが、どうか趙を討つのはおやめになって、人民を休養させ、諸侯の出方をごらんください。
恐れ入って来る者はてなずけ、驕れる者は討ち、無道な者は滅ぼすのです。
そのうえで諸侯に号令すれば、天下を平定することができます。
必ずしも急いで趙を討つ必要はありません。
〝臣に屈して天下に勝つ〝とはこれをいうのです。
もしわたしの意見を聞かずに、あくまで趙を討ち、わたしを罪に陥れるつもりなら、それは、〝臣に勝って天下に敗れる〝こと。
臣に勝って威厳を示すのと、天下に勝って声威を高めるのと、いずれがまさっておりましょうか。
明君は国を愛し、忠臣は名を愛す、敗れた国はもとにもどらず、死せる兵卒は生きかえらぬ、とか申します。
敗軍の将たるよりは、むしろ誅に伏して殺されるほうがましです。
どうかわたしの意とするところをご推察いただきたい」
昭王はものも言わずに立ち去った。
こうして王命に従わなかった白起は昭襄王に追放され、死を賜ることになる。
このときの白起の心情を「白起」ではこう書く。
■「白起」塚本青史著
長平の戦いの後、その勢いに乗じて趙の国都・邯鄲を攻めようとした白起に撤収命令がくだる。
その一年後、秦は邯鄲を攻める。なかなか陥落しない邯鄲を、昭襄王は白起に攻めさせようとする。
しかし、白起は「誰が指揮しても今の邯鄲を落とすことはできない」と、出馬を拒否し続ける。
病と称して自宅に引きこもる白起に、王は、「寝ながらでも指揮をとれ!」と言う)
白起は、何もいう気がしなくなった。
これはもう政策ではない。武安君白起を威に従えさせようとの、単なる意地だ。
親政に目覚めた王の、目の曇りである。
あるいは意のままにならぬ、自分より格段優れた才能への嫉妬かもしれなかった。
邯鄲へ行きさえすれば、たとえ敗れても咎めはなく、行かねば罪なくして罰を蒙ることは判りきっている。
しかし、白起は出馬しなかった。
(中略)
抗命事件により、白起は流刑になり、都・咸陽を出る。そこへ王からの使者が追ってきて白起に2つのものを手渡した。
王から『自決せよ!』との命令書と、柄と鞘に螺鈿を施した短剣だった。
爵位は失っているものの、これは列侯に対する処遇だ。
自決すべき理由は、流罪裁きに不平を述べたこととされている。
そのような事実はない。范雎が捏ちあげたに過ぎない。
この処置は、単なる白起への反感からだけではなさそうだ。
邯鄲攻略がはかばかしくないので、この際、和議を申し入れた方が得策だとの空気が強いのだ。
王は、白起に『それ見たことか!』と言われたくない。
また、趙へは、長平大殺戮の仁義に悖る首謀者を処刑したとて、秦への憎悪を和らげる材料になる。
どうせもう秦のために働く気がないのなら、役立つよう死に花を咲かせてやろうとの魂胆が見てとれた。
この白起の抗命事件の根底には白起と范雎との対立があったと見る意見もある。
もちろん史記にあるように、蘇代がした范雎への耳打ちも対立の引き金だったが
それ以前にお互いをよく思っていなかったのではないか。
その感情を宮城谷氏の著作に見る。
■「青雲はるかに」宮城谷昌光著
上党を攻略しようとする昭襄王と范雎(はんしょ)は、誰に軍を任せるかを話しあっている。
※范雎は魏の人。後に秦に行き、昭襄王に仕え、宰相となる。
「秦に王はいない。いるのは宣太后と魏冉だけだ」と痛烈に現状を指摘した范雎の言をとりいれ、
昭襄王は秦王室を私物化する魏冉と宣太后の一派を一掃することに成功。
失脚した魏冉はもう一つの封邑・陶への引退を余儀なくされた。
「武安君しかおりません」
范雎がそういったとたん昭襄王はいやな顔をした。
武安君、すなわち白起は、魏冉とひとつ穴の狢で、
魏冉が私腹を肥やすのを大いにてつだった男ではないか。
たしかにその武威には非凡なものがあるが、武略において、恣暴(しぼう)がある。
ここで立てた策戦にその行動はおさまりきれず、超越して暴走するきらいがある。
(中略)
結局仕方なく白起に軍を預けることになる。
白起が暴走しないように范雎は釘をさす使者をおくるが白起は反応をしめさない。
范雎は不快に感じた。
白起の性格を悉知(しっち)しているわけではないが、
かれが秦の遺臣のなかでただひとり尊崇したのは魏冉であろう。
その魏冉を追放したのが范雎であれば、白起が范雎を憎むのもむりはない。
しかしながら白起は魏冉の臣ではなく、昭襄王の臣である。
昭襄王をないがしろにしてきた魏冉をよしとしてきたことを反省すべきであるのに、
王朝のありかたを匡矯(きょうきょう)した范雎にあいかわらず悪感情をもっている白起は、
頑冥としかいいようがない。
― 社稷の臣にはなれぬ男だ。(下巻P345)
※社稷の臣とは「国家の安危・存亡を一身に受けて、事にあたる臣。(広辞苑)」
この范雎に対する白起の感情が「奇貨居くべし」にあるのでちょっと載せておく。
この二作品は同時期のできごとを違う角度から見ていて、読み比べると一層おもしろい。
■「奇貨居くべし」宮城谷昌光著
追放令を下された魏冉のかわりに呂不韋が白起のもとへ借金を取り立てにいく場面。
白起は二倍にして借りた金を返す。もちろん小説の中のお話。
そのときの白起の言葉。
「わしが左庶長のとき陶侯から、いや、あのころは穣侯か、その穣侯からお借りした金だ。
それから二十八年がたった。
いまや、韓、魏、楚は秦の盟下となり、残る国は斉と趙と燕になったというのに、
おとなしくなった韓と魏をわざわざ敵にまわし、
遠い斉と結ぼうとする愚蒙の臣が、玉座の近くにいる。
残る国は三国であるといったが、趙を滅ぼせば、あとの二国は抗戦をあきらめて秦に屈する。
趙を攻めるには韓と魏を敵にまわしてはならない。
童子でもわかるようなことを、今代の王はおわかりにならぬ。
これで秦王が天子になるときが、五十年おくれる。
せっかく陶侯が秦王のために天命を受ける壇を築いたのに、
秦王はみずからその聖土を壊徹なさった。
わしのいうことが、わかるか」
白起の憤懣がほとばしった。
※ここでいう愚蒙の臣とは范雎のこと。
范雎は、これまでの秦の方針を一新して「遠交近攻」策というのを実現させようとした。
史記の白起・王翦列伝では、長平の戦い後の対処をめぐって白起と范雎の関係は悪くなったとしている。
宮城谷氏の二作品も、塚本氏の「白起」でも、范雎が魏冉を追放したときから、すでに対立が始まっている。
つまり、白起と范雎はお互いに相手が秦に害を及ぼすのではないかと危惧している。
違うのは范雎には王がついていたことだ。
結局、白起は昭襄王に疎まれ、自刎させられた。
その後も白起の言のとおり邯鄲は落ちなかった。
邯鄲の陥落は秦王政(始皇帝)の時代まで待たねばならなかったのである。
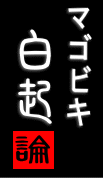 |
◆ 目 次 ◆ 序 1.史書にない白起像 2.白起はどれだけ強かったか? 3.白起をとりまく人間関係 4.戦国時代最大の戦争・長平の戦い 5.白起の大量殺戮の背景 6.抗命事件と白起の最期 7.年表で見る白起の時代 8.参考文献一覧 |
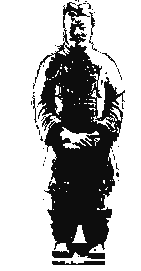 |