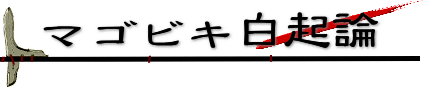
(2)秦の常勝将軍・白起はどれだけ強かったか?
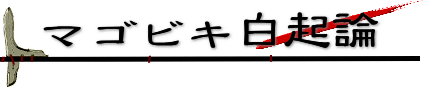
(2)秦の常勝将軍・白起はどれだけ強かったか?
武安君(白起)、秦のために戦いて勝ち、攻めてとるところのもの七十余城。 南はエン・郢・漢中を定め、北は趙括の軍を禽にす。 周・召・呂望の功といえどもこれよりも益さず。 (かの周公旦・召公セキ・太公望呂尚の功績もこれには及ばない) ― 司馬遷 『史記』 白起王翦列伝(蘇代の言) 楚は陳へ逃げた時点で形骸化したといっていい。 楚を実質的に滅ぼしたのは、白起であったといえる。 この戦闘を通じて、白起軍が殺した楚兵は三十万にのぼった。 捕虜に対しても、白起は容赦しなかったのである。 過酷というよりも、戦いの結果そのものが、彼の全人生といってもよいであろう。 彼は戦いの権化であった。 ― 伴野 朗 『邯鄲盛衰』 楚の疆をもってせば、天下、当たること能わず。 白起は小豎子のみ。 数万の衆を率い、師を興してもって楚と戦い、一戦してエン・郢を挙げ、 再戦して夷陵を焼き、三戦して王の先人を辱めたり。 而るに王、これを悪むを知らず。 (とても楚に対抗しうる強国がほかにあろうとは思われぬ。 しかるに現実は秦将白起のごときコセガレの、わずか数万の兵と戦って、 たちまち国都エン・郢を奪われ、祖廟を焼かれ、祖先のみたまを辱めた。 王はこのことを怨みに思わないのですか」) ― 司馬遷 『史記』 平原君虞卿列伝(毛遂の言) 「秦軍が迫ってきたようです」 「秦将の名がわかりますか」 「白氏であると兵はいっておりました」 「伊闕の白起ですね」 「伊闕とは……」 「十一年前に秦は伊闕というところで韓と魏の軍に大勝したのです。 そのときの秦将が白起で、かれが殺した敵兵は二十万とも三十万ともいわれています。 恐ろしい将軍です」 ― 宮城谷昌光 『奇貨居くべし』 白起という将軍は敵ととりひきをしない。 かれは骨の髄まで武人であり、戦いに政治をもちこむということをしない。 それゆえ白起と戦う者は、純粋な勝負にひたりきって、おのれの生死を賭するしかない。 が、白起をうち負かした将軍などいないのである。 ― 宮城谷昌光 『青雲はるかに』 |
 白起は軍事の天才である。
白起は軍事の天才である。
これは誰もが認める史実であろう。
白起は宰相の魏冉に推挙され(史記・穣侯列伝)、数々の戦いで将軍を歴任。
戦況をうまく活かし、戦いに勝ち続け、順調に昇進。
楚の国都を陥落させた功績から、封邑を授かり武安君となる。
まず史記の記述から白起の軍功をみてみよう。
■史記 白起・王翦列伝第十三 (参照、岩波文庫・史記列伝1)
秦のビの人。用兵にたけ、秦の昭王につかえた。
(中略)
昭王13年
左庶長として兵を率い、韓の新城をせめた。
昭王14年
左更になり、韓・魏を攻め、伊闕で戦い、首を取ること24万。
韓の将軍・公孫喜をとらえ、5城をおとす。
国尉となり、黄河を渡り韓の安邑を奪い、東方の乾河に達す。
昭王15年
大良造になり、魏の都を攻めておとし、大小の城61城をうばう。
昭王16年
客卿の錯とともに垣の城を攻めおとす。
昭王21年
趙を攻め、光狼城をおとす。
昭王28年
楚を攻め、エン・鄧など5つの城をおとす。
夷陵を焼き払い、東方の竟陵に達す。
このため、楚王は郢から脱出し、東へ逃げて陳に都を遷す。
秦はうばった郢に南郡をおく。
白起は昇進して武安君と称せられ、それを手はじめに楚の各地を放略し、巫郡と黔中郡を平定した。
昭王34年
魏を攻めて華陽をおとし、将軍茫卯を敗走させて、三晋(韓・魏・趙)の大将たちをとらえ、首を取ること13万。
趙の将軍賈偃と戦ったときには兵卒2万人を黄河で溺死させた。
昭王43年
韓のケイ城を攻めて城5つをおとし、首をとること5万。
昭王44年
韓の南陽を攻めて太行山への通路をたち切る。
昭王45年
韓の野王城を伐ち、この城は秦に降服して、上党から韓の都への通路はたたれた。
昭王47年
長平で趙の軍に大勝し、趙の兵士40万は白起に降服するが、白起は反乱を恐れ、40万人をだまして生き埋めにする。
ただ年少のもの240人だけは趙へ帰してやった。
陥落させた都市の多さも、記録的だが、驚くべきはその捕虜の多さである。
ざっと見ただけでも敵兵を100万人近く斬首(もしくは溺死・生き埋め)にしている。
とくに最後の「長平の戦い」での40万人の生き埋めは凄まじい。
趙という一つの国の成人男子がいっぺんに殺されたのである。
かれの残虐行為の背景には、当時の秦は厳格な法治国家であり、「首級をあげる」ことが昇級の鉄則であったからだと考えられている。
しかし、この桁はずれの戦功は彼自身の破滅につながっていく。
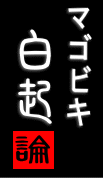 |
◆ 目 次 ◆ 序 1.史書にない白起像 2.白起はどれだけ強かったか? 3.白起をとりまく人間関係 4.戦国時代最大の戦争・長平の戦い 5.白起の大量殺戮の背景 6.抗命事件と白起の最期 7.年表で見る白起の時代 8.参考文献一覧 |
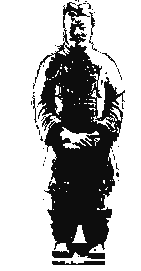 |