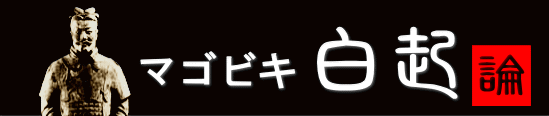 戦国時代最強の武将・白起。功多き彼の最期は意外にも長年つかえた君主からの自害命令だった。 そんな白起にまつわる記述を勝手にあつめてまとめたページです。 <序> |
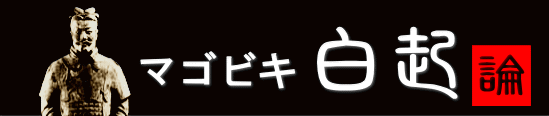 戦国時代最強の武将・白起。功多き彼の最期は意外にも長年つかえた君主からの自害命令だった。 そんな白起にまつわる記述を勝手にあつめてまとめたページです。 <序> |
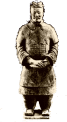
白起という名の人物をご存知だろうか?
中国戦国時代の秦という国の人。
秦の昭襄王に仕えた武将である。
昭襄王とは、あの始皇帝の曽祖父にあたる人物だ。
もっといえば、白起が攻める攻めないでもめた当時の邯鄲(趙の国都)には幼ない政(後の始皇帝)が父親・子楚と人質暮らしをしていた、と考えると時代がつかみやすい。
昭襄王は、群雄割拠の時代において、秦という国を一歩抜きん出た強国に仕上げた王である。
つまり秦の始皇帝が天下統一を果たす礎を築いた王といってもよいだろう。
その昭襄王の時代に秦軍を率いて東奔西走し、他国に秦軍の恐怖を植えつけたのが、この白起という人である。
昭襄王がもっとうまく白起を使えていたら、始皇帝を待たずに天下統一を果たしていたかも知れない、と言ったら言い過ぎだろうか。
白起が歴史に登場するのは紀元前294年、、韓の新城を攻めたところからだ。
翌年、伊闕(いけつ)の戦いで勝利をおさめたのを皮切りに次々と功績をあげ、封邑を授かり武安君と呼ばれた。
その勝ちっぷりは凄まじく、常勝将軍の名をほしいままにした人物と言えよう。
「白起の軍が攻めてくる」
韓の君臣は戦慄し、守城の構えを厚くした。
韓にかぎらずどこの国の軍も、かつて白起と戦って勝ったためしがない。
『青雲はるかに』宮城谷昌光
白起と聞いて「長平(地名)で40万人を生き埋めにしたヤツだな」とすぐにわかったアナタはすばらしい。
卒四十万人、武安君に降る。(白起に降服した士卒は四十万人にのぼった。)
(中略)
すなわち詐りを挟みてことごとくこれをコウ殺す。(そこで、はかりごとをもうけ、ことごとく生き埋めにしてしまった
『史記・白起王翦列伝』司馬遷
私なぞ、春秋戦国時代のゼミを取っていたにもかかわらず、知ったのは卒業してから。
そう、その名と出身と略歴を知ったのは、宮城谷昌光さんの「青雲はるかに」を読んだとき。
そのときは「魏冉(ぎぜん・秦の宰相)の手下の悪いヤツ」ぐらいにしか思わなかった。
南陽にいる昭襄王のもとにもどった范雎(はんしょ・秦の宰相)は、四十余万の捕虜を白起がコウ殺したことを知って唖然とした。
民とは国力の源ではないか。
四十余万の趙兵を秦の民にかえれば、それだけ秦の国力は上昇する。
白起はそのことを考えず、しかも昭襄王の聴許も得ずに降兵を殺した。
天下に昭襄王の悪名をひろめたようなものである。
『青雲はるかに』
次に宮城谷さんの「奇貨居くべし」を読んだら、「思ったより悪くないヤツだな」と思った。
(白起のセリフ)
「趙を攻めるには韓と魏を敵にまわしてはならない。童子でもわかるようなことを、今代の王はおわかりにならぬ。
これで秦王が天子になるときが、五十年おくれる。
せっかく陶侯(魏冉)が秦王のために天命を受ける壇を築いたのに、秦王はみずからその聖土を壊徹なさった。
わしのいうことが、わかるか」
白起の憤懣がほとばしった。
『奇貨居くべし』
最近、塚本青史さんの「白起」を読んだら「ちょっと可哀想なひとだな」と思った。
白起もこの時代の功労者にありがちな悲運の最期を遂げる。
(抗命事件により、白起は流刑になり、都・咸陽を出る。そこへ王からの使者が追ってきて白起に2つのものを手渡した。)
王から『自決せよ!』との命令書と、柄と鞘に螺鈿を施した短剣だった。
爵位は失っているものの、これは列侯に対する処遇だ。
自決すべき理由は、流罪裁きに不平を述べたこととされている。
そのような事実はない。范雎が捏ちあげたに過ぎない。
この処置は、単なる白起への反感からだけではなさそうだ。
邯鄲攻略がはかばかしくないので、この際、和議を申し入れた方が得策だとの空気が強いのだ。
王は、白起に『それ見たことか!』と言われたくない。
また、趙へは、長平大殺戮の仁義に悖る首謀者を処刑したとて、秦への憎悪を和らげる材料になる。
どうせもう秦のために働く気がないのなら、役立つよう死に花を咲かせてやろうとの魂胆が見てとれた。
『白起』
先日、伴野朗さんの「邯鄲盛衰」を読んだら「ある種の天才だな」と思った。
白起は郢を陥落させると、矛先を西の夷陵に向けた。
夷陵は、長江の要衝であり、この地を抑えた戦略的価値は大きい。
白起は夷陵を焼き払うと、兵を東に返し、竟陵に至った。
漢水とその支流沱水の合流点を扼する拠点である。
白起の戦略眼はすばらしい。
これで郢の東と西の戦略拠点をともに抑えたことになる。
白起は、楚を制することは、長江とその最大支流漢水を扼することと同意語であることを知っていたのである。
長江の持つ戦略的価値が定着するのは、三国時代の呉である。
戦国のこの時代、長江の戦略的価値を見抜いた白起は、けだし慧眼であった、といわざるを得ない。
『邯鄲盛衰』
今読んでいる安能務さんの「始皇帝」では秦の「国民的英雄」だ。
(呂不韋のセリフ)
「咸陽城(秦の国都)は長平戦役の勝利に酔っていました。凱旋将軍白起の人気は大変なものです。
方々の街角に俄か拵えの舞台が出現して、城民たちが好き勝手に ― 白将軍かく戦えり を演じながら踊り狂っておりました。」
『始皇帝』
むむ、読むたびにイメージが変わる。
これは「史記」とか「戦国策」も読んでみねばなるまい。
ようするに、私は白起を通して歴史っていろんな解釈があるものだと再認識したわけである。
いろんな作家さんが、同じような史料を読んで、そこにいろんな想像を織り交ぜて、古人を生き生きと描写する。
そこに活躍する人物像は無数の可能性がある。
おもしろい。
白起を残忍で冷酷な、まさに虎狼の国・秦を絵に描いたような憎むべき将軍ととっても可であれば、
一兵卒から実力で栄光を手にいれた天才ととってもよい。
また、白起が、ただ単に好戦的で自分の力量を天下に問うために戦い続けたと考えてもいいし、
一途に秦の繁栄と天下統一を願った忠臣であったと考えてもよいだろう。
彼の抗命事件と自害についても、権力闘争に負けた不器用な武官のなれの果てととるか、
軍事を預かるものとして譲れない名誉と矜持を貫いた潔い姿なのか、それは考える人の自由である。
そもそも2000年以上も前の話である。
史実とされていることですら一つの見方であって、絶対ではない。
そういうことに思いをめぐらせ、想像する楽しみを知った記念としてこのページを作成した。
引用した書物のほとんどが、白起のために書かれたものではないし、部分的に私が自分勝手に引用することによって、
その本のイメージや評価を下げてしまうかもしれない。
それも、私の一個人の解釈にすぎないし、実際、どれもすばらしい作品なので是非ご自身の目で読んでいただきたいと考えている。
そんな言葉をいいわけに、このページの序とさせていただこう。
オマケ。「マゴビキ」について。
 「孫引き」っていいますよね?
「孫引き」っていいますよね?
引用文をさらに引用すること。
原文にあたらず、ひとの論文の訳や見解、注釈をそのまま自分の論文に載せちゃったりして、
「孫引きはいかん!」と先生方は、よく私のような落ちこぼれ学生におっしゃっていました。
そんな孫引きだけで押し切ってしまうという、無茶苦茶なページがこの「マゴビキ白起論」です。
ほかのページと違って、一人でも多くのひとに白起の功績を知ってもらいたい!とか全然考えてません。
純粋に自己満足の世界なので、引用の仕方とかがおかしい!とか思う方もいらっしゃるかも知れませんがご容赦ください。
まぁ、「私はこう思う!」的なお話は勉強になるので、もしご意見のある方は、メールでも掲示板での書き込みでもしてください。
ただ、私は歴史論議を戦わせるほど、精通していないのであしからず。
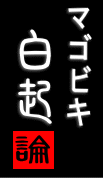 |
◆ 目 次 ◆ 序 1.白起はどこからきたか? 2.白起はどれだけ強かったか? 3.白起をとりまく人間関係 4.戦国時代最大の戦争・長平の戦い 5.白起の大量殺戮の背景 6.抗命事件と白起の最期 7.年表で見る白起の時代 8.参考文献一覧 おまけ・高平焼豆腐 |
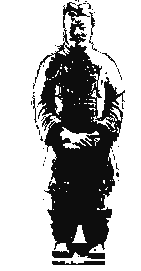 |