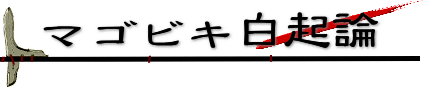
(3)白起をとりまく人間関係
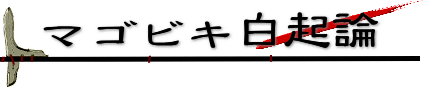
(3)白起をとりまく人間関係
 白起は、数々の武勲をたてた人でありながら、歴史的な評価は高いとは言えない。。
白起は、数々の武勲をたてた人でありながら、歴史的な評価は高いとは言えない。。
その理由は捕虜にした敵国の兵士をことごとく殺してしまったことと、
秦王室を私物化した魏冉に力を貸しつづけたことにあるようだ。
大虐殺については(1)の軍功のところで述べた。
ここでは白起と魏冉・范雎・昭襄王の関係について見てみよう。
<1>魏冉(ぎぜん)
白起を主人公に書いた塚本青史著「白起」でも、白起は「魏冉の子飼い」と位置づけている。
これらはおそらく「史記・穣侯列伝」の
「白起は穣侯が推挙して任用された人であり、親密なあいだがらであった(岩波文庫・史記列伝1)」
という部分に基づくものであろう。
魏冉とはどのような人物か。
魏冉とは、このときの秦王・昭襄王の母であった宣太后の異父弟。
つまり、昭襄王の叔父にあたる人物。
穣(じょう)というところに封ぜられたので穣侯とよばれる。
秦の恵文王、武王の代から官職につき信任されていた。
武王が没すと、魏冉が武王の弟・則を昭襄王として即位させた。
昭襄王は幼く、宣太后が政事をみ、魏冉に政務をまかせた。
秦の領土を増やし、魏の国都・大梁の包囲して、
諸侯たちを秦に仕えるようにさせたのは魏冉の功である。
(史記・穣侯列伝第十二より要約)
この魏冉と白起の関係をよく表した現代の著作を引用させてもらう。
■「奇貨居くべし」宮城谷昌光著
秦のため、といいつつ、自領をふやし、充実させてゆくのが魏冉(ぎぜん)のやりかたである。
白起は魏冉に抜擢されたので、公私混同の魏冉を批判することなく、
魏冉の命令にしたがいつづけてきた。
白起は戦場において卓犖(たくらく)としており、当代随一の名将であるが、
魏冉の私行に手を貸しつづけたという倫理の欠如が、生涯の瑕瑾(かきん)であり、
その名が後世において暉映(きえい)を失ったのもわからぬではない。(火雲篇P22)
<2>范雎(はんしょ)と昭襄王
范雎は、それまで秦の顔だった魏冉を追放し、昭襄王を親政に目覚めさせた人物である。
白起が長平の戦いで勝利をおさめたのは、范雎の作戦が功を奏したからである。
二人が趙の廉頗と藺相如のように国家の両輪となって秦を支えていたら、昭襄王の天下統一も夢ではなかったかもしれない。
しかし、現実には、白起の手柄に嫉妬した范雎が、白起に邯鄲を攻めさせまいと、先手をうって趙と和議を結んでしまう。
それを知った白起は范雎と仲たがいをしてしまう。
結局、講和をしたものの、一年して秦は趙の邯鄲を攻めようとする。
しかし、何十年と戦場を駆け巡った白起の目には、今の邯鄲は陥落不能とうつった。
ここで、「邯鄲攻め反対の白起」対「どうしても邯鄲を陥としたい昭襄王と范雎」という構図ができてしまう。
白起の反対を押し切る形で始めた邯鄲攻めだが、白起の言ったとおりに邯鄲は一向に落ちない。
そればかりか、秦軍の被害ばかりが報告される。
最後の切り札である白起は范雎が頭を下げても、昭襄王がじきじきに命令をしても病気を理由に出馬しない。
あげくのはてに「秦は私の意見を聞かなかったばかりに今はこのざまよ」と白起が朝廷を批判してるという噂まで飛び出す。
これを聞いた昭襄王はおもしろくない。
結局これがもとで、白起は自害に追い込まれる。
白起が魏冉の部下であったから、范雎も昭襄王も白起のことを以前からよく思っていなかったかのかもしれない。
また、強い将軍は王にとっては頼もしくもあるが、同時に謀反を起こされたらたまらないという恐怖もある。
実際、そう疑われて悲惨な運命をたどった武将は枚挙に暇がない。
それを考えると、王の命令にしたがわなくなった白起は朝廷にとって危険人物であったのだろう。
かりに昭襄王が天子となろうとも、いずれ白起は殺されていたのかもしれない。
その辺が武将の限界といえばそれまでだが、使い捨てのようで可哀想だ。
さて、その范雎と昭襄王について見てみよう。
范雎とはどんな人物か?
昭襄王とはどんな人物か?
■「青雲はるかに」宮城谷昌光著
上党を攻略しようとする昭襄王と范雎(はんしょ)は、誰に軍を任せるかを話しあっている。
※范雎は魏の人。後に秦に行き、昭襄王に仕え、宰相となる。
「秦に王はいない。いるのは宣太后と魏冉だけだ」と痛烈に現状を指摘した范雎の言をとりいれ、
昭襄王は秦王室を私物化する魏冉と宣太后の一派を一掃することに成功。
失脚した魏冉はもう一つの封邑・陶への引退を余儀なくされた。
「武安君しかおりません」
范雎がそういったとたん昭襄王はいやな顔をした。
武安君、すなわち白起は、魏冉とひとつ穴の狢で、
魏冉が私腹を肥やすのを大いにてつだった男ではないか。
たしかにその武威には非凡なものがあるが、武略において、恣暴(しぼう)がある。
ここで立てた策戦にその行動はおさまりきれず、超越して暴走するきらいがある。
(中略)
結局仕方なく白起に軍を預けることになる。
白起が暴走しないように范雎は釘をさす使者をおくるが白起は反応をしめさない。
范雎は不快に感じた。
白起の性格を悉知(しっち)しているわけではないが、
かれが秦の遺臣のなかでただひとり尊崇したのは魏冉であろう。
その魏冉を追放したのが范雎であれば、白起が范雎を憎むのもむりはない。
しかしながら白起は魏冉の臣ではなく、昭襄王の臣である。
昭襄王をないがしろにしてきた魏冉をよしとしてきたことを反省すべきであるのに、
王朝のありかたを匡矯(きょうきょう)した范雎にあいかわらず悪感情をもっている白起は、
頑冥としかいいようがない。
― 社稷の臣にはなれぬ男だ。(下巻P345)
※社稷の臣とは
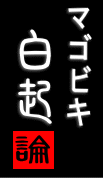 |
◆ 目 次 ◆ 序 1.史書にない白起像 2.白起はどれだけ強かったか? 3.白起をとりまく人間関係 4.戦国時代最大の戦争・長平の戦い 5.白起の大量殺戮の背景 6.抗命事件と白起の最期 7.年表で見る白起の時代 8.参考文献一覧 |
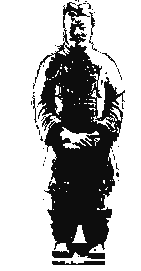 |