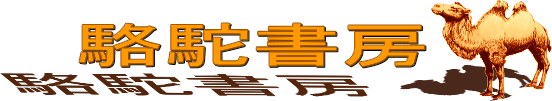 |
 |
|
| - Luotuo Shufang Top -China series - Rakuda no Nichijyou - Special Thanks & Links - Luotuo BBS - mail - | ||
| 駱駝電影院がいっぱいになってきたので、「書籍」の部を独立させてみました。 駱駝が最近読んだ本の感想を書かせてもらってます。 映画以上に偏りがあるから、参考にもなんないけど、 もし、共感してくださる方がいらしたらお友達になってください。  |
||
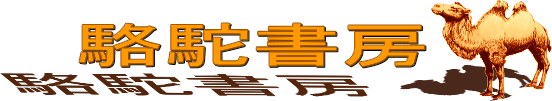 |
 |
|
| - Luotuo Shufang Top -China series - Rakuda no Nichijyou - Special Thanks & Links - Luotuo BBS - mail - | ||
| 駱駝電影院がいっぱいになってきたので、「書籍」の部を独立させてみました。 駱駝が最近読んだ本の感想を書かせてもらってます。 映画以上に偏りがあるから、参考にもなんないけど、 もし、共感してくださる方がいらしたらお友達になってください。  |
||
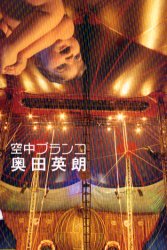 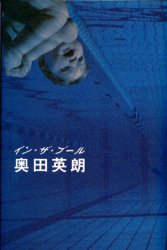 |
2005/4/29 イン・ザ・プール 空中ブランコ (奥田英朗/文藝春秋) 珍しく売れている本を読んでみました。と言っても姉の蔵書を勝手に読んでみたら、けっこう売れてるらしい、と後で知ったんですが。そういや、めざましテレビのランキングで上位に入っていたような。短編集で、「イン・ザ・プール」の続編が「空中ブランコ」(逆かと思ってた!)。確かに面白い!軽いので気楽に読めて、忙しい方にもちょいと息抜きにいいかもしれません。普通じゃない精神科医・伊良部先生のもとについつい通ってしまう患者さんのお話。どっちが医者だかわからんほどハチャメチャなやりとりが笑えます。無邪気でずうずうしい伊良部先生に、ひそかに舌打ちする患者さんの心の中のツッコミが好き。こんなんで症状が良くなるわけないと思う治療法(?)でも、伊良部先生の天然ペースに乗せられているうちに、なんとなく希望が持ててくるところが安心して読めていい。マンガ化はすでにしていて、今後、映画化やドラマ化もするみたいだけど、ぜひ原作を読んでもらいたいですな。 |
|
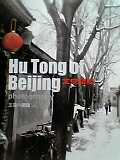  ① ② ※実際はどちらも正方形に近い横長の装丁です |
2005/2/6 ①北京胡同(Hu Tong of Beijing) (中国旅游出版社) ②北京四合院(QUADRANGLES OF BEIJING) (北京美術撮影出版社) 四合院について知りたくて、MUSTAFAさんに北京で買ってきて頂いた2冊です。 ①は胡同の写真集です。よくお土産で売っている胡同の絵はがきや、日本でも出版されている胡同の写真集の徐勇さんの写真をはじめ、ちょっとレトロないい感じの写真がたくさん。中・英・日の3ヶ国語で書いてあるが、日本語はよくよく読むと不思議な文章。 ②は四合院建築を写真と文章で紹介する本。こちらは中・英2ヶ国語。門の種類や、門の土台石、内装などについての概要が写真とともに掲載されている。この本こそ日本語で読みたいところ。じっくり読むと、やはりビジュアル重視なのでもう少し詳しく知りたくなってくる。導入本としてはぴったり。 |
|
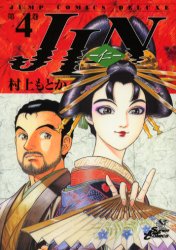 |
2005/1/29 JIN-仁- 1〜4 (村上もとか/ジャンプコミックスデラックス/集英社) 「龍」とセットで借りてきた「JIN」です。同じく村上もとかさんの作品。「現代の医師が江戸時代にタイムスリップしてアオカビからペニシリン作ったりしちゃっておもしれぇんだよ〜」とはMAPPY氏の言だが、まぁその通りの話です。知識はあっても器具や医薬品がない中で治療を続ける主人公。ついには自分までもコレラにかかってしまったりと苦労の連続。「龍」にもまけず、幕末の人物がじゃんじゃん登場してきます。幕末のお話はいろいろあるだろうけど、医学にスポットをあてたところがナイスですな。これこそは4巻で完結かと思ったら、こっちもまだ執筆中。わ〜っ、続きが気になるっちゅうねん。やりかけの宿題が2つもたまったようでいやだわ。早く続きでないかなぁ。 |
|
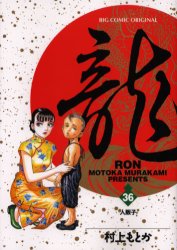 |
2005/1/27 龍-RON- 1〜37 (村上もとか/ビッグコミックオリジナル/小学館) 今月38巻が出るらしい。戦前の京都からはじまって、舞台は大陸中国へ。財閥の一人息子が気が付けば上海マフィアのボスになったり、女中さんが大女優になったりと、もう大変なことに。しかも実在の人物もじゃんじゃん出てきて話は大きくなるばかり。よく調べてあって面白い。ありえない話だけど楽しめる。ただし、うっかり読んでしまうと長いし、まだ完結してないので、すっきりしないことウケアイ。 思えば「龍-RON-」を初めて読んだのは98年。広州の宿舎で隣のイエンツァンさんが毎号取り寄せてるビッグコミックオリジナルを借りて読んだときのこと。しばらく遠のいていたけど、このたび、MAPPY氏がガツンと37巻までまとめて貸してくれたもんだから、寝不足の日々が続いたわ。6日かかってやっと37巻。でもまだまだ終わりそうもないのが困ったもんです。一巻一巻発売されるの待ってられないなぁ。 |
|
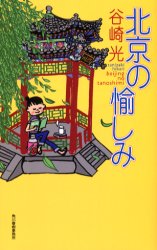 |
2004/12/27 北京の愉しみ (谷崎光/角川春樹事務所) 現在北京在住のてなもんや商社の谷崎さんがおくる通な北京の愉しみ方。万里の長城や、故宮なんていうメジャーな観光地もよいけれど、当地人しか知らないようなお寺や胡同、茶館、市場など、作者もちょっと教えたくなかった秘密のよい所が満載。今度北京に行ったら、四合院のお宿に泊まって市場で茶器を買い、胡同をまわり、安くておいしい北京ダックを食べようと、いろいろ考えてしまうことウケアイ。北京の世界遺産は見尽くしたリピーターに是非読んでもらいたい一冊。読んだが最後北京に行きたくなってしょうがなくなります。昨年出版されたので新しめの情報ですが早めにいかないともうこのスポットはないかも。洒落た上海よりどこか古風な北京を味わいたい方はお早めに。 |
|
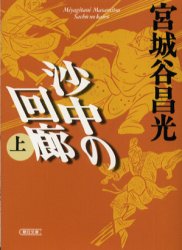 |
2004/12/17 沙中の回廊 上下 (宮城谷昌光/朝日新聞社) ひさしぶりに宮城谷さんの小説をよみました。宮城谷さんの作品にしては珍しく題名で誰の話か想像できないけど、主人公は春秋時代の晋の武将(でいいのかな?)「士会(しかい)」。この名前だけでピンとくる方はすごいですな。時代は初めのころが、「晋の文公」、終わりの方があの3年鳴かず飛ばずの「楚の荘王」といえばだいたいつかみやすい。宮城谷さんの「晏子」の冒頭で斉で恥をかかされ激怒した晋の「郤克(げきこく)」が師事したのがこの「士会」。この本は文庫化して朝日文庫で出版されているんだけど、本屋さんには文庫のほうはあまりおいてないのがネック。でも読んでみて、置いてなくてもいいかな?って感じ。夢中にさせられるような躍動感や、入れ込みたくなる人物描写が足りない気がするのよね。派手な功績のあった人じゃないからかもしれないけど、淡々としていて、歴史や哲学的な解釈ばかりが目につく。男の一生を書く小説としては他の作品のほうが楽しかったな。 今チェックしたら、朝日文庫のほかに文春文庫からでていて、しかも文春のほうが安いです。私はネットで中古を買ったからいいんだけど。。。 |
|
 |
2004/11/11 客家円楼 中国・福建省・広東省・江西省 (岡田健太郎/旅行人ウルトラガイド) 「巨大な住宅土楼建築を見に、1週間で行く徹底ガイド」という表紙の言葉どおりのガイドブックです。円楼とは中国南部に点在する、円柱形をした独特な建築方法で建てられた住宅。巨大なものになると何百人ものひとが暮らせるほど、大きな住宅で、上から見ると輪を幾重にも重ねたような、なんとも絵心をくすぐられるユニークな形をしている。中国の切手にもなっていて、中国や建築物の好きな人にはたまらない、あこがれの家です。ただ、交通の便がイマイチな田舎にあるので気軽に行けないのミソ。そのため、ついこの前までは、まだツウな人しか行ったことがなかった。そんなときに、円楼を目指す人のバイブル的な存在になったのがこの「客家円楼」というガイドブックのようだ。あちこちのかなりマイナーな土楼を細かく紹介。装丁がちょっと自費出版みたいな雰囲気なのもまたいい。著者の方に続く第一人者(第二?)Ginaさんのお話ではここ数年の間に急速に観光地化が進んでいるそうです。便利になる反面、素朴さが失われつつあるかもしれません。鄙びた感じが好きな方は早く行きましょう!私もとっても行きたいのですが。。。 |
|
 |
2004/10/15 ブレーメンⅡ⑤ (川原泉/白泉社) 男性の方にはあまりご縁がないと思うけど川原泉さんのマンガです。ここに載せるのは初めてですが、この人のマンガは全部ウチにあったりします。少女漫画だけど、めちゃくちゃ字が多くてきらいな方もいらっしゃるかと思いますが、私は好きです。でも正直、最近のはイマイチかな。昔の「笑うミカエル」とか少しあとの「美貌の果実」「中国の壺」あたりがやっぱり好き。「バビロンまで何マイル?」も題材がよくて期待していたわりに、イタリアの話で終了でがっかり。もっと一つを短く、いろいろなネタで続けてほしいのにな〜。そんで期待持ち越しで、次に出たのがこのブレーメンⅡのシリーズ。SFです。ブレーメンⅡという貨物宇宙船の船長さんと乗組員(全員ゴリラとかカンガルーとかの動物)がいろんな星に行っては事件が起こるというような話。もう五巻目なんですな。で、この巻で終了のようです。ん〜、また次作に期待かな。川原さんには、未来とかじゃなくて、もっと身近なキャラクターで、ちょっとインテリぽくてでも笑えるギャグを書いて欲しいな。最近、わたしゃ、こ難しい話にちょっと根気がつづかないからな、笑いを期待しますわ。絵はきれいになったけど、内容は以前のほうが楽しかったな〜。 |
|
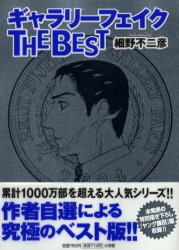  |
2004/10/13 ギャラリーフェイク THE BEST ギャラリーフェイク 31 (細野不二彦/小学館) あんまり同じマンガを載せてもつまらないないでしょうな〜。こう見ると駱駝図書館も代わり映えのないコーナーですね。なかなか新しいものに手を伸ばす余裕がないのバレバレですわ。 ともあれ、ギャラフェです。30巻を載せるのを忘れましたが、ちゃんと読んでます。今回は作者本人が選んだベスト版なんてのが出てましたので、一緒にご紹介しましょう。ベスト版なので、全部読んでるひとには、読んだことあるお話ばかりですが、巻末に1話だけ、書き下ろしが載っているので、ちょっとうれしいかも。メトロポリタン時代の藤田のお話がなかなかよいですよ。ギャラリーフェイクを読んだことない人も、とっかかりには調度いいので読んでみては?モネの積み藁とかフェルメールの合奏の話が入ってます。31巻はまたジャンポール香本さんがまたもや登場。細野さん、けっこうこのキャラクターすきみたいですね。最近三田村館長の影が薄い気がするのは私だけ?まぁ、すっごいいい話が載っているわけじゃないけど、相変わらず、へぇ〜!という薀蓄満載の一冊でした。 |
|
 |
2004/06/25 埼玉のことば(県北版) (篠田勝夫/さきたま出版会) 北埼玉の方言をひそかに集めている私にもってこいの本が出版されました。厚めのハードカバーなんですが、内容は辞書。よくもこんなに集めたもんです。1万語ちかい方言をアイウエオ順に整理し、語源や用例などが細かに掲載し、さらに特徴のある語に関してはエッセイ風の囲み記事がついています。例えば、「たまげる」は「魂(たま)消ゆる」が変化したものなんですって。知ってました?それって方言ってほどではないんじゃ?と思えるものもあれば、そうそう言う言う!というものも、そんなの聞いたことない!ってのもあります。3,800円(税別)というちょっと高めですが、興味のある方には価値ある一冊です。作者の方は10年かけて、収集したとか。すごいですねぇ。こんなの出された日にゃ、私の立場ないですな。駄馬氏によれば熊谷の八木橋デパートの本屋さんで売上ランキング9位に入っていたらしいです。私のほかにどんな人が買ったのだろう?お友達になりたいな。 |
|
 |
2004/06/20 青のメソポタミア (秋里和国/白泉社文庫) 久々に秋里さんのマンガです。高校生のころよく回し読みしたなぁ。でもこのマンガは知らなかった。古本屋さんで見つけ、歴史物かな?とぼんやり想像して買ってきました。実はSFでした。高度な文明をもつ惑星エンリルっていう星の人間が古代の地球を発見し、調査に行くという話に、王位争奪の陰謀が絡んでくるというストーリー。このエンリルって星はアッカド王朝の支配下にあって、シュメール家という王族が出てきて…というと、歴史に詳しい人はなんとなくオチが分かったりして。こういうありそうでない発想が面白いと思います。こんな話を思いつけば、小説の一本も書けるんだろうなぁ。 |
|
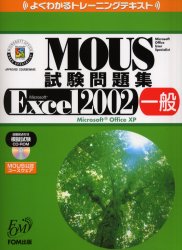 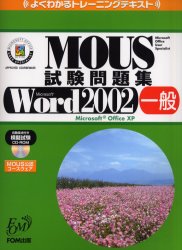 |
2004/03/29 MOUS試験問題集 (FOM出版) 見てその名のとおり、MOUS試験の問題集です。もっとも今はMOUSではなくMOSというのですが。MOSとは、マイクロソフト・オフィス・スペシャリストの略だとか。数多く出版されているこの手の問題集のなかでも一番評判がいいのがこのFOMからでている問題集。前半の「スキルとタスク」という問題を通しで2回ぐらい勉強し、その後付属の模擬をやれば、たいていの人が合格できるようです。パソコン教室の先生は模擬を何回もやると、問題を覚えてしまうので「スキルとタスク」を何度もやりなさい、言っていました。この問題集のいいところは、問題と回答が載っている箇所とは別に、同じ問題が、問題文だけ小冊子にまとめられいて、切り離せるところです。ですので、答えを見ずに実力が試せるわけです。もちろん模擬のCD−ROMを使うと本番によく似た形式で自動採点もしてくれます。ただ、模擬の模範解答はあくまで回答例の一つなのであまり鵜呑みにしないほうがいいかな。なにはともあれ、私はこれで合格したのでオススメです。ちなみに2003の試験がはじまってないので、まだ2003用は出版されていません。なのでWord/Excelの2003では模擬試験は起動できませんのでご注意。2003用の問題集は5月ごろ出るそうです。 |
|
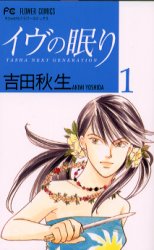 |
2004/02/20 イヴの眠り1 (吉田秋生/小学館/別コミフラワーコミックス) 「YASHA」の続編です。つぎの世代ってことで、シンの息子とルーメイの娘のお話です。まだ新人類の遺伝子が残っていて、クローンが作られ、さぁ大変みたいな話になりそうです。シンが初代中国の大統領におされそう、などと、さらに話が大きくなりそうです。「BANANA FISH」ではチャイナタウンの悪がきだったのにすごい出世です。1巻には「YASHA」の外伝が載っていて、その後、どうなって「イヴの眠り」に続くか分かるようになっています。「YASHA」の終わり方があっけなくて、がっかりしていたら、続編ときたもんです。だったら、続くとか書いてくれよ〜。年末の大掃除で「YASHA」全巻ブックオフに持っていっちゃったよ。ま、「YASHA」のほうに続編の布石なんてなさそうだから、読み返す必要はないからいいけどね。 |
|
2003/11/16 中国語表現ポイント99 (東方書店) 何年か前に東方書店で買ってきたこの本を、ふと中検を機に開いてみたら、けっこういい本かなぁ、と思いました。オビにあるように通じる中国語から正しい中国語へのステップアップのための本です。私のような「さまよえる中級人」にぴったりの内容です。大きさは新書版で小さいので持ち運びも便利です。ちゃんと覚えれば、かなりためになるんでしょうが、すぐ忘れちゃうんですよね。似たような単語や表現の使い分けや、微妙なニュアンスの違いを説明してくれます。辞書代わりにするには少し説明が少ないのですが、他にはない知りたかったことが載っているので助かります。もっと細かい説明を書いた進化版がほしいですな。 |
||
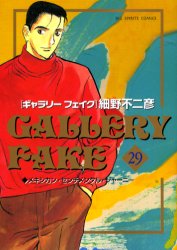 |
2003/11/14 ギャラリーフェイク (細野不二彦・小学館) 最新刊が出てました。文庫版がなかなか出ないから、最近では諦めて大きいのを買っています。最近フジタの「いい人度」が目立つのが気になります(悪徳画商なのに。)が、相変わらず次から次へとよく題材を探してくるもんですな。ちらっとフェルメールのターバンの女(見たことない方はこのページの下のほうのオランダの本の表紙を見てください)が出てくるけど、細野さん、もっときれいに描いてって思う。ほかの絵はけっこうきれいに描いているのに。でもターバンの女は確かに描きにくいのよね。一見単純なポーズなんだけど微妙に首をかしげているせいか、一歩間違うと目がオカルトっぽくなるの。やっぱフェルメールはすごい。もしギャラリーフェイクの絵を一枚くれるとしたら迷わずターバンの女がほしいな。 |
|
 |
2003/10/3 かいしゃいんのメロディー (竹書房・大橋ツヨシ) 私の大好きな4コマ漫画。悲しいけど、これが最終巻だそうです。主人公の「うずら谷」さんの名前から、私はこの漫画を「うず」と呼んでいます。これは好き嫌いがあるだろうな。私は好きなんだけどね。大橋さんのすべての作品が面白いとは思わないけど、このシリーズと「喜怒愛楽一家」ってのが好き。どういうのって、ちょっと表現できない、独特の世界なんだよね。しかも4コマ漫画なんて、書店にあまり置いてないから、立ち読みもオススメできないんだけど、もし見かけたら、是非、開いて見てください。ちなみに、この巻にはあまり出てこないけど、うずら谷さんの同僚の左右さんちの猫がとっても好きです。 |
|
 |
2003/08/13 アジアンノットを楽しむ (雄鶏社) 多趣味な私だが、こんな女らしい手芸にハマッたのは最初で最後かもしれない。一見、私、手先が器用そうに見えるでしょ?でも裁縫とか大っ嫌いなんだよね。家庭科はいつも居残りだったし。メガネ屋やってたときは、よく壊してお客さんに謝ったし。そんな私に、ちまちまと、アクセサリーを作らせちゃったのがこの本。アジアンノットっていうと洒落てるけど、ようは中国伝統芸・組みひもだよね。これってよく中国のお土産なんかで、注文するとその場で好きなパーツで結んでくれるよね?あの不思議な結び方がこの本を見れば、普通のひとでも出来ちゃうってのがすごくない?中国人のおばあちゃんがひそかに伝えていく伝統芸かと思ったのに!そう思うとやらずにはいられないのが性分で、イライラしながらも、ついつい夜なべをして完成させてしまう。寝不足になるので要注意。ほかにも組みひもの本はいくつか出てるけど、これが一番センスいいと思います。是非一緒にはまりましょう。 |
|
 |
2003/08/01 始皇帝 中華帝国の開祖 (安能 務・文芸春秋) 現在我々が抱く始皇帝像は、そのほとんどが秦を倒して興った漢の時代に書かれた文献によるところが多い。だから、始皇帝を良く書くはずがなく、暴君の代名詞のように扱われているが、もっと公平にみたら天才的な政治家であるというのが、この本のテーマ。エイ政の生い立ちからその死までを、政治とは何か、権力とは何か、法とは何かをつきつめて描いている。政治の話になるとむずかしくてわかったような分からないような、って感じ。安能さん、頭良すぎ。それはともかく、この安能さんの歴史を見る目はとても好感がもてる。史書をうのみにしない。もちろん書かれたことには意味があるのだから、否定はしないけど、そのどこまでがあり得ることかきちんと分析してくれる。史記の刺客列伝では剣が長くて抜けずブザマに逃げ惑う始皇帝が書かれているが、衛兵が命令がなくて動けないとしても、シークレットサービスがいただろうし、武官だってたくさんいたはずで、主治医が薬箱を投げただけというのはあり得ない、そうだ。たしかにそうよね。まちがっても「HERO」みたいにサシで勝負なんてしないわな(笑)。焚書坑儒や民に過酷な労役を課したとかいわれているけど、それも言いがかりくさい。なぜ、不老不死を求めたかも自然な欲求だとか、いろいろ説明してある。これを読むと始皇帝と韓非子は本当に天才だなって思う。 |
|
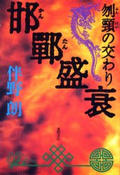 |
2003/06/24 邯鄲盛衰 刎頚の交わり (伴野 朗・徳間書店) 「邯鄲」といえば、趙の国都、「刎頚の交わり」といえば廉頗と藺相如だ、ってことが、今さらながら分かるようになってきた。春秋戦国時代のゼミをとってたくせに。よく卒業できたな。それにヒキカエ、今はちょっと戦国時代オタクよ。だから、この題名見て、すぐに買おうと思ったわけ。伴野さんの「刺客列伝」は昔、何度も読んだから、親近感もあったしね。内容はもちろん、廉頗と藺相如、それと趙奢などの趙の人がメインなんだけど、塚本さんの「白起」と同様、同世代の人のことも一通り書いてある。「白起」より分かりやすいから、予備知識がなくても楽しめる。いろいろ親切に解説してくれるしね。意外に悪役の白起のことを詳しく書いてあって、白起びいきの私はちょっとうれしかった。でも、白起の字(あざな)と享年はどこから導き出したの?史記にも戦国策にも書いてなかったと思うけどな。創作かな?話はそれるけど、横山光輝の「史記」のイメージが強いからか、白起は壮年の将軍、廉頗は、おじいちゃん将軍って感じがする。でも実際は白起のほうが年上じゃないかな?よし今度そこんとこ追跡してみよう。さて、本題。この本では秦=昭王&白起で、魏冉の影はない。いままで読んだこの時代の小説は、秦=魏冉&白起だったから、ちょっと新鮮。白起=魏冉の部下って構図は不動かと思ってたから、そういう見方もあるのね、って感心。欲を言えば、趙の滅亡までもっと詳しく書いてほしかったな。最後が駆け足すぎる。私はむしろ長平の戦い後の廉頗について詳しく知りたかった。それ以外はよかったです。刎頚も交わりの下りはとくに感動です。 |
|
 |
2003/06/19 中国の思想Ⅱ 戦国策 (守屋 洋訳・徳間書店) 「白起」を読んだら戦国策を読まずににはいられない。でも戦国策の本って少ない。全訳っていうのもなかなかないし、原文が載っているのもなかなかない。この本と明治書院の新書版は抜粋だけど、原文と書き下し文が載っているので、どっちにしようかまよった。決め手は白起の故事が載ってるからこっちにした。思ったよりよかった点は巻頭に戦国時代とはどんな時代であったか、というのが項目ごとに分かりやすくまとめてあること。訳文も平易な文章でスーッと頭に入る。戦国策の一話一話は、ごく短い。だから、どういう歴史の流れでそうなったかはわかりにくいけど、ドラマチックなセリフが面白い。ちょっとウソっぽいと思わなくもないけど、史記にはない伝説じみたヒーロー像を楽しめる。 |
|
 ↑「マゴビキ白起論」↑ 作成中!請等一下! |
2003/06/18 白起 (塚本青史・河出文庫) 白起という人をご存知だろうか?中国戦国時代の秦の武将にして生涯で100万人規模の記録的大虐殺をした、まさに乱世が生んだ人物。だから中国史の中でもどちらかっていうと悪名が高い。かと言って彼は狂人というわけではなく、法治国家の秦にあって信賞必罰の軍律をまっとうした一武官であったと思う(秦王との最後の意地のはりあいはともかくね)。白起には負けた記録はなく、まさに常勝将軍で、その強さたるや、秦の宮廷人ですら眉をひそめたとうのだから、白起に対する敵国の兵の恐怖はいかばかりか。輝かしい軍功を残しながら、彼の最後は史記や戦国策に見えるように、王の怒りをかって、一士卒に身分をおとされ自害させられる。その悲運の武将が生きた時代のわかりうる全てを書いてしまったのがこの本。白起の昇進をことさらにドラマチックに描写するでもなく、いたって冷静な文体(漢字はやたらと難しい)で同世代の魏ゼン、范雎、武霊王、廉頗、藺相如、楽毅、孟嘗君、蘇秦、呂不韋などの歴史の中心にいた人々の動きをまとめ上げている。これを読めば、紀元前300年から前250年ぐらいまでの各国の猫の目外交がよくわかる。一見、史実そのまんまと思えるような感じだが、少ない資料でよくここまでストーリーを結びつけたものだと、感心させられる。同世代を書いた宮城谷さんの「青雲はるかに」も想像力に富んでいて面白かったが、この塚本さんもすごい。やっぱ作家さんてすごいなぁ。みんなよく史実にこれだけの裏話を考えつくもんだ。巻末の解説に、作者のたどった道を確かめたくて史記や戦国策を調べたと、あったが、私も衝動的に両方とも書店で買ってきてしまった。史記の人物像と戦国策のそれはちょっと違う気がするし、宮城谷さんと塚本さんもまたちょいとちがう。その違いを楽しむのもまた一興。歴史の解釈のバリエーションは尽きないもんですな。白起を死にいたらせた范雎について書かれた「青雲はるかに」と合わせて読むと面白い。本当はみんな、どんな人たちだったんでしょうね? |
|
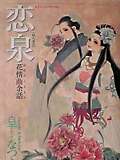 |
2003/06/10 恋泉―花情曲余話(れんせん―はなのこえよわ) (皇なつき・あすかコミックスDX・角川書店) 皇(すめらぎ)さんの絵はきれいだ。皇さんの作品はストーリーも楽しみに違いないが、なんといっても絵の美しさが魅力。これだけの画力があるのは羨ましいかぎり。先日暇つぶしに読み返した井上祐美子さんの「長安異神伝(徳間ノベルズのほうね。文庫版のカバーはきれいな絵でしたが)」の挿絵と比べると雲泥の差だな。あれぐらいなら、私にも描ける。中国系の小説に挿絵をつけるなら、全部、皇さんに頼みなさい、って思う。へたっぴな挿絵など要らんばかりか、想像力の妨げになるもん。ま、それはともかく、このマンガは花情曲(はなのこえ)の第2巻。といっても短編集だけどね。時代は唐、花仙を娶った青年を軸に伝奇的なお話が展開する。ようは、中国歴史ファンタジーとでもいう部類かな。少女むけの甘い話だけど、それはそれ。個人的には「黄土の旗幟の下(李自成の話、主人公は違うけど)」みたいな、メルヘン色があまりないもののほうが好きだけどね。実はこの後に読む「白起」だけでは送料がかかるので、ちょうど1,500円(超えると送料はサービスなの)になるようにネットでこの本を頼んだの。でも絵のきれいさに大満足。次の「白起」の世界とのギャップがすごいだろうな。メルヘンの後に大量虐殺者の話とは、私もセッソウがないな。 |
|
 |
2003/06/10 創竜伝 13 (田中芳樹・講談社ノベルズ) この小説とは長い付き合いという人は私の周りにはけっこういると思う。根本は中国系だからな。中高生ぐらいから読み出して、今でも最新刊が出ると、つい買ってしまう。銀英伝は読む気しないんだけどね。一応「創竜伝」をご存知ない方に簡単な説明をすると、東京に住む四人兄弟が、実は人界で転生を繰り返す天界の竜王の117代目だったりするの。で、世界を牛耳ってる4財閥・フォーシスターズとかと戦ったりする。中国の神話だか道教の思想だか(実は私もよくわかってない)をもとにしたファンタジー小説。四兄弟の可笑しいやりとりや、現代社会の皮肉がたっぷりなシリーズ。昨日、本屋さんで平積みになっているのを発見したけど、多分、発行されたのもついこの間だろうな。あとがきが5月5日になってたから。だから、内容もイラク戦争とか、新しい話題が早速ヤリダマにあげられている。登場する日本の首相が病気にみせかけ殺されそうになって、かわりに能無しの巨漢が密談で新首相になったりすんの。名前こそ違うが明らかにオブチさんを連想させる。もっとも、小説のなかでは死んだりしないけどさ、大丈夫なの?よく発行禁止にならんね。右の人が読んだら焚書にするぜ。ファンタジー小説という形をとって田中芳樹の思想がふんだんにばら撒かれている感じ。中高生のころはなんとなく感心していたけど、今読むとちょっと抵抗がある。ま、言ってることは間違ってないとは思うけどさ、現にちょっと圧力が掛かりかけたみたいだし、いつかこの作者、暗殺されるんじゃない? |
|
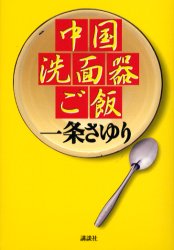 |
2003/05/13 中国洗面器ご飯 (一条さゆり・講談社) ひょんなことで、LEEさんに薦められた話題本です。中国ではお昼時、店員さんたちがホーローの器でご飯を食べているのをよく見かけますが、これを作者の一条さん風に言うと「洗面器ご飯」だとか。中国の広州に暮らして出会った人のお話や体験をエッセイ風にまとめてあります。留学生宿舎にいては平和すぎるとして犯罪都市広州を味わうべくマンションに引越するというのがお見事。日本人なら当然感じる中国人とのギャップや、いろんな疑問を回りの中国人友達に聞いてたどりついた一応の結論など、中国と関わった人なら少なからずうなずける一冊です。私は広州にいながら、現地の人と仲良くなって理解を深めるなんてしなかったから、一条さんのように積極的に中国人を知ろうと努力するひとをとても尊敬してしまう。なんらかんら言って私は小心者で、平和な大学の敷地でのんべんだらりとした日々を送ってしまったことにちょっと後悔。ともあれ、広州でなくとも、中国好きなひとから、中国と韓国の区別もつかない人まで、中国に興味のある人は読んで損はないと思います。カメゼリーの前後に大根を食べるなと言ったお兄さんの言葉の謎もこの本で納得。この本を読んでたら、スカートなのにくるぶし丈のストッキングを履いている中国人のファッションをおかしいと主張してくじけたこととか、白いワンピースに下着が透けて見えるのはどうかと思うと意見して逆に言いくるめられたこととか、楽しくも困惑だらけだった留学生活を懐かしく思い出すことウケアイです。広外同学、読むべし!ちなみに一条さんは天河区にある学校だったとか。それってジーナン大学?あの辺の地理はさっぱりだわ。 |
|
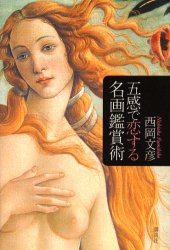 |
2003/05/15 五感で恋する名画鑑賞術 (西岡文彦・講談社) 名画は好き嫌いで見ればよい。絵の名札は見ずに額縁は見る。美術館で全部をじっくり見る必要はなく好きな絵、目当ての絵をじっくり見ればよい。それで一番好きな絵だけはよく覚えておく。でその絵を自分が好きな理由を考えると自分が見えてくるとか。そんな名画の見方と、ルネッサンス以降の絵画の歴史について簡単に書いてある本です。17世紀のオランダの画家フェルメールはカメラを使って絵を描いたっていう話が載っているのでつい買ってしまったのだけど、まぁまぁ、おもしろかったかな。鑑賞術って言うほどのもんでもないけどね。ワシは元から好き嫌いでしか見てないからな。ロココとかバロックだとか、何とか派だとかさっぱり分からん。でもこの本に載っているくらいの画材の変化の歴史などは分かっていたほうがいいし、勉強になった。それと鑑賞法のオマケとしてちょっと勇気づけられたのはグッズは「買い」だということ。美術館のグッズとか、ついついみんなほしくなっちゃうんだけど、高いからなぁ、って思っているうちに諦めてしまう。でもこの本は迷ったら買え、という。自分のためのお土産として、好きな絵と、見たときの印象を留めておくために買うべし、と。もう一度出向いて買うことを考えたら、少々がさばるとか高いとかは問題ではない。絵はがきは自分用と友達用に2枚買え、というのも納得。そうだよね、今度からは迷わず買おう。 |
|
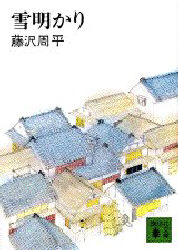 |
2003/05/04 雪明かり (藤沢周平・講談社文庫) 常務先生からお借りした藤沢周平第二弾。これも短編集です。この本の主人公は貧乏侍とか、本当は気のいいヤクザな町人とか、気丈な町娘とかで、ささいなコトの裏側で人知れず起こっている人情話がテーマって感じかな。短いながらも、わりと容赦のない展開だったりする。時代小説って池波さんもそうだけど、必ずしもハッピーエンドでなくて、けっこうあっさり人が死んじゃったりするのね。だから切なくていいのかもしれないけど、個人的にはちょっとほほえましい「冤罪」ってお話がよかった。貧乏なお侍さんは長男でなければ婿養子に行くしかなくて、常にいい婿入り先はないかと考えてたりしているのが新鮮だった。時代小説を書く人ってよく調べてるよね。何を元に当時の生活とかをこうもうまく表現できるんだろう。尊敬だな。 |
|
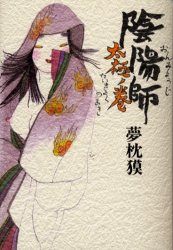 |
2003/04/28 陰陽師 太極ノ巻 (夢枕獏・文芸春秋) 久々にマンガじゃないものを読みました。とは言っても、軽い短編小説ですが。陰陽師は相変わらず字が少ない。この倍ぐらいの量になってから一冊にしてほしい。東京への一往復で読み終わってしまうなんて、損した気分。それに、ちょっと展開が見えすぎ。読んでて、こういうオチじゃないかな?って想像がついてしまう。マンガのほうの陰陽師も何やら別物っぽくなってきて、読みたいと思わなくなってきたし、そろそろ飽きてきたのかな、ワシ。。。面白いことは面白いんだけどね、昔ほど魅力を感じなくなってきたかも。う〜ん、次は文庫本でいいかな。 |
|
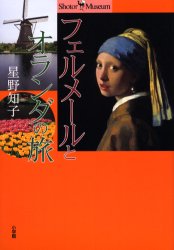 |
2003/03/21 ショトル・ミュージアム フェルメールとオランダの旅 (星野知子・小学館) ギャラリーフェイクを読んで、美術熱が上がり、本屋でレンブラントとフェルメールの画集(タッシェン・ニュー・ベーシック・アートシリーズ)を買ったらフェルメールにハマってしまい、レンブラントもフェルメールも同時に見れるオランダに行きたくなりました。私みたいな人は絶対いる!と思い、「オランダ名画の旅」みたいな本を探していて見つけたのがこれ。2000年の日蘭交流400年を記念して開かれた「フェルメールとその時代展」(←今さらながらすっごい見たかった!)に合わせて発行された本らしい。私はこの作者で女優の星野知子さんってよく知らないんだけど、心のこもったいい文章を書く方ですな。惜しむらくはこの本、すごく薄いので、すぐ読み終わってしまうところ。カラーの写真でわかりやすい解説も満載でこの薄さで1700円でもいいかな、とは思うんだけど、もっと読みたい。作者の星野さん自身、すごくフェルメールがお好きなようで、絵に出てくる白いデカンタを求めて骨董屋をまわったら、「牛乳を注ぐ女」のアンカやタイルを見つけたなんて話が、すごく面白い。今年はゴッホの生誕150周年らしいし、ゴッホの初期の油絵が見つかったりと、オランダと言えばゴッホのイメージだけど、私は、やっぱり、フェルメールを見に行きたいな。でもワシ英語できんし。一緒に「オランダ名画の旅」に行ってくださる方大募集! |
|
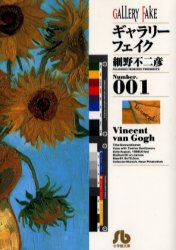 |
2003/01/21 ギャラリーフェイク 001〜004 (細野不二彦・小学館) このマンガ、まだ連載中なのかな?オリジナルの単行本は26巻まで出ているらしい。私が知ったのはつい最近。姉が買ってきた文庫版を借りて読みました。文庫版はまだ数巻しか発行されてないのでまどろっこしい。ま、短編だから、続きがどうのってわけじゃないけどね。題名からもピンとくるように画商のお話。設定は元・NYメトロポリタン美術館の学芸員の藤田玲司っていう人が主人公で、「ギャラリー・フェイク」というギャラリーを営む傍ら、裏では真作を法外な値段で売買するっちゅうわけ。世界の名画や彫刻、例えばモナリザやミロのヴィーナスから、日本の焼き物や刀まで、そのテーマごとに「よく知ってるなぁ」ってなお話が展開される。「美味しんぼ」の美術版みたいな感じ?学芸員ってそんなことまでできるんか?って思わないでもないけど、へぇーって感心しながら楽しめます。多少、美術に興味のある人のほうが面白いって思えそう。知ってる絵とかでてくるとうれしいし。あ、私ね、レンブラントが好き。一度本物がみて見てみたいっすよね。キリコの話とか呉王コウリョの剣の話なんてのもあって結構興味津々で読んでます。お話は面白いから、この細野さんっていう作者の絵がもうちょっとうまいといいんだけどね。 |
|
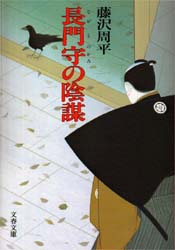 |
2003/01/14 長門守の陰謀 (藤沢周平・文春文庫) 「たそがれ清兵衛」の話をしていたら、成り行きで常務から「まぁ、ヒマなときにでも読んだら?」って渡されたのがこの本。私は初の藤沢周平です。実はもう一冊借りてるんだけど、まだ読んでない。せっかくなら「たそがれ〜」を貸してほいかったなぁ、常務。時代物だけど、読みやすい。常務曰く、藤沢さんの小説は江戸時代のお侍さんと今のサラリーマンがだぶるような人情物だそうだ。でもこの一冊は表題作を除けば、主人公はお侍ではなく、江戸時代の女性ですな。舞台は江戸時代なんだけど、常務の言うように、なんとなく今の世にも通じる人間ドラマが展開されるところが魅力かな。この本は短編集なんだけど、出てくる旦那や彼氏はどれもパッとしない。そんな連れ合いをちょっと不満に思っている女たちの感情の行方。そして垣間見た男たちの意外な素顔。なんとなく分かるなぁ、などと納得してしまう一冊。話の終わり方が読者の想像の余地を残すところは、この人の特徴なのでしょうか。時代ものといえば池波さんの男くさい話ばかり読んでいたので、結構新鮮だったでしたな。 |
|
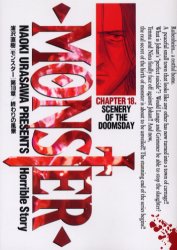 |
2002/12/30 MONSTER 1〜18 (浦沢直樹・小学館) キートンの次はやっぱりコレでしょ。舞台はドイツ、そしてチェコ。主人公は日本人の天才脳外科医テンマケンゾー。院長の娘と婚約し出世間違いなしといわれたテンマ。ところが、亡命してきた家族が襲われ、重症の男の子を執刀した日から、彼の人生は翻弄されていく。テンマに命を救われた男の子ヨハンをめぐる陰謀、旧体制、東側の恐るべき計画、そしてヨハン自身の企み。最初のうちはそうでもないけど、どんどん色んな人が出てきて、そして殺され、複雑化していきます。怖いし、難しいし、可哀想だし、悲しいお話。先がよめない展開で、読み出したら止まりません。途中でやめるとやな夢見そうです。いつも指をかくかく動かしているルンゲ警部と、「ヨハン、ステキナナマエナノニネ。」のフレーズは忘れられません。あなたの中のモンスターは大きくなってますか? |
|
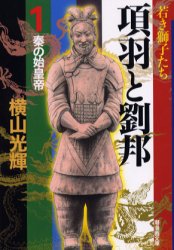 |
2002/12/22 若き獅子たち 項羽と劉邦 1〜21 (横山光輝・潮出版社) え〜っ、駱駝ってば、項羽と劉邦も読んだことなかったの???って思われそうですが、いかにも!読んだことなかったんです。おかしいよね?それでも中国文学科か!と誰もが思うことでせう。見かねたM氏が貸してくれたのは左のような文庫版じゃなくて、昔のコミックサイズのものです。ま、内容は同じでしょう。始皇帝の時代から、漢の統一までを書いた有名なマンガですね。項羽といえば、「虞や虞やなんじをいかんせん」の詩しか知らなかった私が、このマンガで張良や韓信なんて名前を覚えただけでもたいいしたもんです。今になってようやく「鴻門の会」がどういう経緯で行われたかわかりました(おせーよ)。講義や授業でハイライトは習っているのよね。でもよく分かってなかったんだな、実は。率直な感想、面白かったっすよ。劉邦はとくに自分の力でどうしたってのは少ないけど、項羽ってば若いのにすごかったね。20万人も生き埋めにしちゃったのも若すぎたからかもな。張良も賢いけど、韓信もすごいね!まじで負け知らず。こういう有能な将軍は決まって終わりがよくないのよね。それを思うと、越の范蠡(春秋の人)はすばらしい引き際だったよな。あ、范蠡は関係なかったっす。でも私の、お気に入り将軍に韓信は登録せねば。で、次にすることは、史記を読んで確かめる。漢なんて私の趣味で言えばかなり新しい時代だな。ドキドキ。。。 |
|
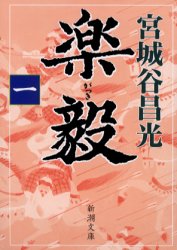 |
2002/12/12 楽毅 1〜4 (宮城谷昌光・新潮文庫) 諸葛孔明をして、この人の御者になりたいと言わしめた名将軍・楽毅(がっき)のお話です。時代は孟嘗君と同じころ、中国戦国時代です。わずかな年月で多くの城を攻め取った伝説の将軍ですが、その有名なお話は4巻の最後の数十ページだけ。では1巻から3巻まで宮城谷さんは何を書いているかといえば、他の作品と同様に歴史に登場するまでの苦労話。戦国時代にひょいと現れた中山国(すぐ滅亡しちゃうのよね)の宰相の家に生まれた楽毅は、将来、中山軍を率いる力量を養うため、国交のない斉の国へこっそり留学し、兵法を学び、帰国するや、蒙昧な中山王の下、趙軍と必死に戦うという、お話。暗愚な君主をささえる有能な臣下ってな構図がこの小説の中に多くちりばめられています。仕える上司を選べない時代って大変だなぁって思いますな。ちなみに史記なんかにも載っているように、後に燕の功労者になった楽毅は、燕王が代替わりすると、新王に嫌われてあっさりと将軍の座から下ろされてしまい、あろうことか処罰されそうになるという、上司に恵まれなかった人です。でも、かっこいいですよ!楽毅は上司に恵まれなくても、楽毅の部下は幸せだったことでしょう。しかし、楽毅が中山の人だっていうのは宮城谷さんの創作だよな?それとも本当?んー、気になる。また調べなくてはいけないことが増えてしまった。。。 |
|
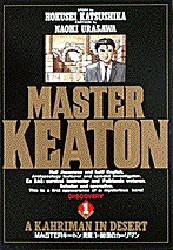 |
2002/11/24 MASTER キートン1〜18 (浦沢直樹・勝鹿北星・小学館・ビッグコミックス) 職場のM氏ご推薦のマンガです。数年前にアニメ化され、深夜にテレビで放送されていたのでご存知の方も多いようですが、私は初めて今回読みました!超オススメ本です。タイトルからは内容が想像しにくいので、ざっと説明しましょう。主人公は平賀=キートン・太一、英国籍の考古学者。日本の大学で講師をするかたわら、保険会社の調査員として、世界中をとびまわり、色々な事件を解決するっていう、いわば探偵もの。なぜ、マスターなのかは、読んでみれば自ずと分かります。このシリーズのすごいところは、ちょっとマイナーな遺跡や、軍事や、ヨーロッパの各国の情勢など、あまり普段は縁のない事を題材にしていること。読み終わると、脳みそのシワが少し増えたって感じっす。見た目はイマイチさえないキートン氏、実はスゴイ、スゴイけどかなり謙虚っっちゅうのがGood!っす。18巻で完結なのが残念。ソ連の崩壊から湾岸戦争など時代を追って書かれてきたのだから、このままずっと続けていてほしい作品です。歴史好きな人は絶対読むべし!!!基本的に一話完結の短編集なので読みやすく、内容も濃いので読み始めたら、ハマります。ちなみに作者はYAWARA!とか、MONSTERを書いてるひとですな。 |
|
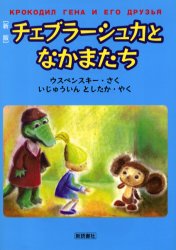 |
2002/10/14 チェブラーシュカとなかまたち (ウスペンスキー・新読書社) sirouさんオススメの児童文学っす。知ってる人は知っている(らしい)「チェブラーシカ」の原作。その名から連想できますが、ロシアの子供たちに長年、親しまれてきたお話だそうです。日本では、旧ソビエト時代に作られた人形アニメ版が、昨年映画公開されて話題になったとか。ジャングルにいた小熊のようなケモノは果樹園でオレンジを食べていたらそのまま箱詰めにされてロシアにやってきました。箱の中で足がしびれていたケモノは、ころんでばかり。それを見た果物屋さんのおじさんは「チェブラーシュカ(よくころぶやつ)」と名づけました。そのチェブラーシュカとワニのゲーナと女の子のガーリャの三人のお話。キュートなチェブラーシュカも魅力ですが、動物園にお勤めのワニのゲーナさんがとても紳士的でステキです。微笑ましい場面がたくさんありますが、謎の生き物「チェブラーシュカ」は一体なんという動物なのか、みんなで考えるシーンが特にお気に入り。ガーリャが「チェブラーシュカはきっと豹だわ!」って言い出して、辞書で「ヒョウ」を引き始めるんだけど、何故か「豹は‘うなる’から‘う’で引くのよ!」「いや、‘かみつく’から‘か’だ!」なんて言い出すの。間違っても豹じゃないよぉ〜って思いながら笑ってしまいました。そのほかにも「自動電話」とか「労働のメダル」とか、勝手に空き地に家を建てちゃったり、なんとなく並んで買い物しちゃう人々とか、何だかとっても共産主義的な雰囲気が味わえるのが楽しいです。DVDも発売されていて、動くチェブラーシュカにも会えます!このかわいさ、ハマリます。 |
|
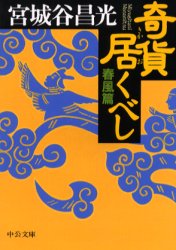 |
2002/10/10 奇貨居くべし1〜5 (宮城谷昌光・中公文庫) この人がいなければ始皇帝も存在しなかったという呂不韋(りょふい)を全五巻という長編で綴った小説です。呂不韋は賈人(商人)でありながら、王位継承は絶望的だった秦の公子・子楚(始皇帝の父)を財力にものを言わせ秦王にし、自身も相国(宰相)になったというスゴイ人だ。でもどちらかと言うと一般的には「姑息な手でなりあがった人」というイメージが強いだろう。始皇帝も実は呂不韋の子だという説もあるくらいだし。でもこの本では呂不韋を中国で初の民主主義を実現させようとした人と位置づけている。彼は若い頃とんでもない苦労を経験しながらも、各国の貴人と知り合い、いつしか民のための国作りをしたいと思うようになるというストーリーである。呂不韋が子楚と出会うまでの紆余曲折は宮城谷さんの想像の域をでないことかもしれないが、「和氏の璧(かしのへき)」まで持ち出すその大胆な発想が尊敬ものである。同じ宮城谷さんの著作「青雲はるかに」や、「孟嘗君」と同時代なのでダブって出てくる人物がいるが、違う角度で書かれたそういう人たちを見るのもまた楽しい。そういう意味で「孟嘗君」「青雲はるかに」「奇貨居くべし」「楽毅」を続けて読むとおもしろいと思う。それにしても宮城谷さんの手にかかると、どんな人も魅力的にみえる。かれらの為政に対する熱意にはいつも感動させられる。でも、どんな敏腕宰相も君主次第で、うまくいってても、多くの場合、王が交代すると新王に疎んじられ失脚させられてしまう。まさに動乱の時代だなぁ、としみじみ思った作品でした。 |
|
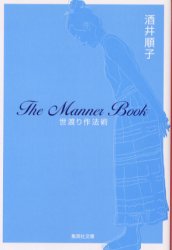 |
2002/10/02 世渡り作法術 (酒井順子・集英社文庫) また姉の本を盗み読みしてしまった。今回のはマナー本。でも、ちっとも説教くさくないどころか、フランクな文章に爆笑です!「そうそう、そういうことってあるある!」って超共感!「そういうヤツっているんだよなぁ」に始まって「やば、私もそんなふうに見られてるかも!」までいろんなシチュエーションが的確に表現されていて感動です。内容は海外旅行はどんな友達と行くべきか?とか、友達の子供がブサイクだったらどうほめるか?とか合コンでのマナーとか、元彼の結婚式の二次会に呼ばれたら?などの社会人の気配りと対策がメジロオシ。既婚者の人なら正月にダンナの実家に帰るべきか?とかご近所づきあいとかも載っていて役立つ(?)かも。私も海外旅行は絶対、同じ価値観の人といくべきだと思うし、コンビニの店員に愛想は無用と常々思ってたけど、こうやって文章で表してもらえると「私はやっぱり正しかった!」とちょっと褒められた気分。とくに20代後半から30代前半の独身女性必読です! |
|
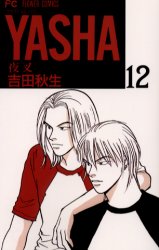 |
2002/09/25 YASHA 夜叉 12 (吉田秋生/小学館/別コミフラワーコミックス) 以前に11巻について書きましたが、この12巻が夜叉の最新巻にして最終巻です。友人から「12巻が最終巻だよ!もう出てるよ!」って聞いて慌てて買ってきました。まさかこんな早く完結すると思ってなかったので、ちょっとガッカリです。これからどんどん話が膨らんでドロドロしていくと思ってたのに、けっこうアッサリした終わり方でした。舞台は主人公「静(せい)」の故郷、沖縄の奥神島(本当にはないよね?)。生産能力の低い、老人や病人、低所得者、発展途上国の国民をウイルスによって抹殺しようと考える製薬会社と政府。それを止めさせようとする「静」たちの最後の戦い。なんかこの巻は詰め込みすぎだな。もっと深く書いてほしかった。華僑のボス「シン」もお笑い担当になっちゃってるし。ま、終わってしまったものは仕様がない。それにしても終わりに近づくにつれ、あまりに「静」と「凛」のメンタルな部分が多くてちょっとひいてしまったのは私だけでしょうか。単に、私が兄弟愛より友情ものが好きってだけでしょうけど、もうちょっと期待してたのよねぇ。今度は香港でも舞台にして「ルー・メイ」を主人公にして書いてほしいなー。 |
|
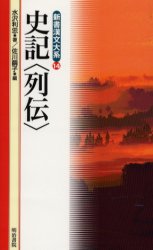 |
2002/09/12 新書漢文大系14 史記(列伝) (水沢利忠・明治書院) 横山光輝の漫画で史記を読んだら、「どこまでが司馬遷の記述なんだろう?」って気になりだして、原文が読みたくなった。でも原文が載っているような本はハードカバーなので気軽に読めない。で、いいのがないかなーと思って本屋さんで見つけたのがこれ。新書版なので電車でも読めるのがいい。中は書き下し文と、注釈と、現代語訳とからなっているので、少しは原文の雰囲気を味わえる。「刺客列伝」は高校生のときから好きだったから何度も読んだけど、他のとこはほとんど手付けず。これを機にちょっと読んでみようと思ったわけです。で、今回私がちょっとハマってるのが「廉頗(れんぱ)・藺相如(りんしょうじょ)列伝」の藺相如。上の「奇貨居くべし」にも藺相如が出てくるけど、めっちゃ格好いいっす。知ってる人は知ってるでしょうけど、彼は「完璧(かんぺき)」って言葉の語源の人です。ついでにいうと、「刎頚の交わり」とは廉頗と藺相如の故事から来ているってことで、逸話の多い人です。たいして身分も高くなかった相如が一国の命運をかけて秦王を相手に同等に駆け引きをするシーンは長い中国史のなかでも名場面の一つと言っていいでしょう。こんなにカッコイイ話をたくさん残してくれて、司馬遷って、やっぱりスゴイ人だ。 |
|
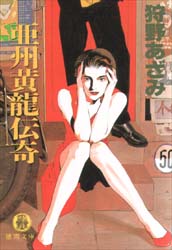 |
2002/09/05 亜州黄龍伝奇1〜7(第5巻は外伝) (狩野あざみ・徳間文庫) 5年くらい前に買ったこの小説をふと読みたくなったのはテレビで香港の風景を見たから。そう、この小説の舞台は香港。通りの名前、建物の名前が実に詳しく描写されている。私にはよくわからないけど、香港に詳しい人なら、登場人物が今、香港のどこを走ってるか、手に取るように分かると思います。新華社とか、14K(サプセイケイ)とか、実在する団体なんかの名前が出てくるところがまたリアルでいい。でも小説の内容は「伝奇」ってくらいだから、かなり現実ばなれしてるので、ファンタジー好きな人にオススメ。かと言ってコバルト文庫とかのノリとは違って、映画でいえば、アクションものになるかな。あー、田中芳樹の「創竜伝」ってあるでしょ?あれの香港版っていうのがいいたとえだな。「創竜伝」も、ようは陰陽五行説がもとになってるでしょ、これもそんなかんじ。「創竜伝」が好きな人なら絶対おすすめ。このシリーズも話が進むにつれ、チベット問題に絡んできたり、中東情勢に絡んできたりと話がどんどん大きくなっていきます。ただ、5巻の隋唐陽炎賦だけは時代もので隋末唐初が時代設定になってますけどね。この手の小説は手軽に読めるのがいいですな。一日2冊のペースで読んでしまいました。ちょっと香港の風に当たりたくなったら是非読んでみてください。 |
|
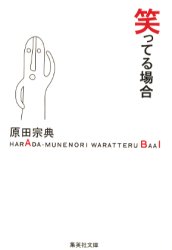 |
2002/08/ 笑ってる場合 (原田宗典・集英社文庫) 大好きな原田さんのエッセイです。エッセイと言えば原田さん。小心者で、必要以上に人目を気にしたり、ちょっと人よりついてなかったりする心境をとっても面白く表現してくれるので、通勤途中で読んだりしたら吹き出したり、ニヤニヤしちゃうので要注意。でも今回のは、おちゃめな原田さんだけでなく、ちょっとダークな話もあったりして、ディープな人物像が垣間見れます。いろいろな出版物に掲載されたエッセイをまとめた一冊なので、短いもの、テーマが決まってるものとかいかにも寄せ集めって感じがしなくもないですが。。。その上、原田さんは「作家なのにエッセイばっかり書いてていいのか?」って思っていたらしく、これからは気の向いたエッセイしか書かないことにして、創作活動に力を入れるそうです。ちょっと私としてはさみしい思いがします。 |
|
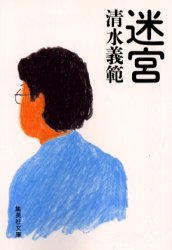 |
2002/08/ 迷宮 (清水義範・集英社文庫) 姉が買ってきたこの本をちょいと拝借して盗み読みしたら、面白くて一日で一気に読み終えてしまいました。ジャンルで言ったら「模倣犯」の類かな。記憶喪失の男が治療と称して、あるストーカーが犯した猟奇殺人事件に関する様々な文章を読まされていく。なぜ自分がこの文章を読まされるのか、この犯人こそが自分なのか、それともこのルポを書いた作家が自分なのか、何もわからずに次々と文章を渡される男。文章の内容は徐々に事件の真相に近づいていくかに見えた。。。本の内容のほとんどがこの男が読んでいる文章という、ちょっと変わった小説です。ストーカー殺人なんて犯す人って、一般的には理解不能。でももし機会があれば、犯人の心理を追求し、納得のいく説明を聞いてみたいと思わない?そんな私の好奇心をくすぐられた一冊です。でも、これ読むと打算的に人とつきあうと痛い目にあうよ、って言われているようで、ちょっと怖い。 |
|
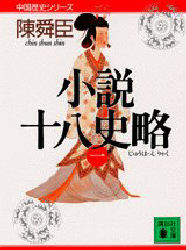 |
2002/07/04 小説 十八史略 (一) (陳舜臣/講談社文庫) 全6巻の小説十八史略の第1巻です。実はこの本は大学に入学するときに買ったものです。、中国文学科に受かったはいいが、けして古典に通じているわけでも、中国史に明るいわけでもないことにあせって、読んでみたのです。当時はそんな義務感に駆られて読んだだけでしたが、読み返してみると、今のほうがダンゼンおもしろく感じました。たいして熱心な学生ではないながらも、講義や小説やらで少しは中国古代史について知恵がついてきたので楽しめる余裕が出てきたのでしょう。実際、とても読みやすい文体で、中国ものなのに「イニシアティブ」とか「マニア」というようなカタカナの言葉で表現されるところがなかなか楽しい。この1巻は神話の時代から始皇帝の統一まで(私が一番好きなトコ)が入ってます。宮城谷さんの本を読んだはいいが、歴史の古い順から読んだわけではないので、時代の流れが私の中で混乱してしまっているので、それを整理するためにこの本を開いてみました。でも、すぐ忘れちゃうんだよな、ワシ。 |
|
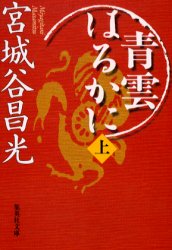 |
2002/06/19 青雲はるかに 上・下 (宮城谷昌光/集英社文庫) 中国、春秋戦国時代の秦の宰相、范雎(はんしょ)のお話です。やっぱ、宮城谷さんのはおもしろい!もっと言えば、長編がいい。すべての作品を読破したわけではないですが、面白かった順でいくと、「晏子」、「孟嘗君」、この「青雲はるかに」が三番ってなトコです。どれも、戦国の世に生まれ、自分の才覚一つで世にでていく男たちを魅力的に描いています。成功したあとの話より、芽が出る前の苦労話がいい。主人公も格好いいがそれを支える人々もいい。あぁ、私もこんな人に仕え一緒に馬車で戦い成功の一端を担ってみたい。ま、范雎は文官だから戟を手に取りなんてシーンはないですが。そういう点では「晏子」のほうが私好み。「青雲はるかに」は少し趣きが違って、大器晩成の男(冤罪で死にかけたりする)とそれを支える美女たちの話。読みやすいので下巻は一日で読んでしまいました。しかし、宮城谷さんってすごい。どれだけの漢籍を読み込んでいるのだろう?中国文学科卒なのに三国志も読んだことない私はただ尊敬するばかり。 |
|
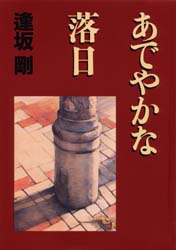 |
2002/05/31 あでやかな落日 (逢坂剛/朝日新聞社) ずっと前から「逢坂剛」を薦められていながらも、何故か手に取る気がしなかったのですが、今回初めてページを開いてみました。私が「模倣犯は重かった」と話していたら「これは軽いから」と言われて読み始めたけど、本当に読みやすかった。逢坂剛と言えばスペイン物が代表作だそうですが、これは舞台は日本。大手家電メーカーの極秘の筈のプロジェクトが雑誌に次々とすっぱ抜かれる謎を、主人公がさぐっていくって話。何故か出てくる女の人はみんな主人公に惚れちゃうんだな。女性も主人公もイヤに魅力的っていう書き方がちょっと鼻につくけど、「誰が犯人?」って感じで、最後までひきつけられる内容でした。でも、中国歴史物ならどんなに格好いい人物の書き方しても許せるのに、この人のは「カッコつけすぎ!」って思っちゃうのは、やっぱり私がスペインにもギターにも興味がないからかなぁ。 |
|
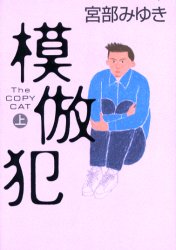 |
2002/05/09 模倣犯 上・下 (宮部みゆき/小学館) スゴイ本だ。5年がかりで仕上げただけある。犯人、犯人の家族、被害者、遺族、警察、マスコミ、ありとあらゆる形で事件に関わった人々の人生とその人生が紡ぎ出す思考が、細かい描写で綴られていく。決して愉快でも楽しくもない、むしろ不快なストーリーだが、そのリアルな人間像にとりつかれたように「何でこうなってしまうのか」という答えがほしくて、読み続けてしまう。どうしようもない後悔、どうにもならない絶望感、それでも自分を見失わない人、自分を見失ってしまう人、自分を見失っていることに気付かない人。本を閉じても後を引く。こんな夢見の悪い本は読んだことがない。いやに考えてしまうのだ。自分にもこういう闇はあるんじゃないか、こういうことって結構あるんじゃないかって暗くなる。それにもまして怖いのが、この犯人のような人は実際にいるんじゃないかと思えてしまうこと。これは確かにミステリー小説だが、人間の心理の見本市のようなもの。映画化なんて無謀だ。2時間でこの話は表せない。映画には期待しないことにしよう。 |
|
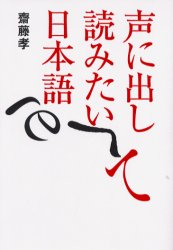 |
2002/04/09 声に出して読みたい日本語 (齋藤 孝/草思社/2001年9月18日第一刷) 国語の授業で暗唱させられた、古典や小説の出だしや、落語の「じゅげむ」など、声に出してよみたい日本語がいっぱい詰まっています。ふいに、「祇園精舎の鐘の声...えーっと何だっけ?」って思ったこと、ありませんか?私は覚えは悪いけど、暗唱って何故かけっこう好きだったので、懐かしく思い、買ってしましました。七草とか、十干十二支とか、最初しか知らないのも続きがわかってスッキリします。個人的には、中原中也は「よごれちまったかなしみに」を載せてほしかったかな。貧窮問答歌とか日本国憲法前文なんてのもチョイスしてほしかったけど、暗くなりそうだしなぁ、まぁ、しょうがない。 |
|
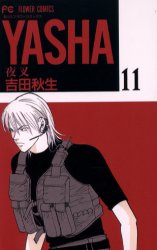 |
2002/03/23 YASHA 夜叉 11 (吉田秋生/小学館/別コミフラワーコミックス/2002年3月20日第一刷) 新刊の11巻がでました。伊藤英明くんのドラマ「YASHA」の原作です。あのドラマはいただけなかった。一話を見て原作との格差にがっかり、それ以降はちっとも見なかった(伊藤くんファンの方スマン!)。よかったのはスティングの主題歌ぐらいだ。やっぱ原作でしょう。こういうジャンルを何と言うのかわかりませんが、「BANANA FISH」同様、少女漫画の枠を超えてます。アメリカの製薬会社が遺伝子操作で作った新人類の双子をめぐるお話。銃、撃ちまくりのけっこうアクション派。「BANANA FISH」のシンも、華僑のリーダーとして出てきます。その辺がけっこう楽しみだったりして。私って、けっこうオタッキー?(本のラインナップを見ると、アニメオタクで占い好きの人間ですよね、やばいかな)。マンガってすぐ読み終わっちゃうのが残念。早く12巻でないかなー。 |
|
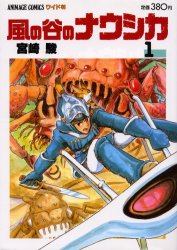 |
2002/01/25 風の谷のナウシカ 1〜7 (宮崎 駿/徳間書店/アニメージュコミックスワイド判/1983年〜) テレビで映画のナウシカをチラッと見て、ふと漫画版をもう一度読みたくなって、ブックオフで買ってしまいました。中学生のときに友人に貸してもらって読んだのですが、ほとんど忘れていました。10年以上昔の作品なのに、古くないと言うか、流行り廃れを超越した宮崎駿さんの想像力には「まいった」の一言です。映画しか見たことのない方、是非、原作を読んでみてください。もっと、壮大なストーリーです。絵のタッチも古い洋書の挿絵みたいで、映画のきれいさとは、また違ったよさがあります。(映画版は、風の谷のおじいちゃんたちがとてもいいですけど。)原作は、もっと続きを描いてほしいところです。でも、あれで終わりだからしょうがないか。 |
|
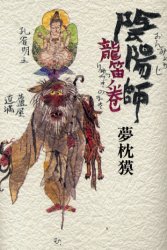 |
2002/01/19 陰陽師 龍笛の巻 (夢枕 獏/文芸春秋/2002年1月15日第一刷) お待ちかね、陰陽師の最新刊です。そろそろ出たはず、と思って本屋さんに行って買いました。楽しみにしていたわりに、すぐ、読み終わっちゃうのが残念。しかもネットで読んでしまった話もあったし。まぁ、あの、短編のアッサリ感がよいのだから仕方ないけど。でも、もう2話ぐらい収録してほしいなぁ。映画も陰陽師2をやるそうで、なかなかのブームだから、小分けに出して、じらす作戦なのかも。大学のときに友人から漫画の方を借りて、小説にもハマッたけど、まさか映画にまでなるとは。小説は晴明と博雅のやりとりがいいですね。漫画の方は絵が好きだったんだけど、どんどん難しくなっていくので、正直、私はよく内容が理解できない。小説の、のんびりした感じがやっぱり好きかな。 |
|
-China series - Rakuda no Nichijyou - Special Thanks & Links - Luotuo BBS - mail - |
||