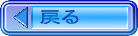駱駝式・盆棚を作ろう!
”今年もお盆が近づいてまいりました。
皆様ご先祖様のご供養のご用意はいかがでしょうか?”
と石材店の宣伝カーが街を走りまわる今日この頃。
”お前も覚えろ!”と強制的に手伝わされた盆飾り。
その第一の難問「盆棚作り」の手順を書きとめておこう。
盆棚を知らん人も、「あ、おばあちゃんちで見た〜!」って人もご覧下さいな。
ちなみに、近所の郷土博物館のよりウチのほうが立派だぜ、といつも思うけど、
それは、じいさまが作っていたから。
じいさまも、もうヨボヨボなので私にもお鉢が回ってきた。
出来上がってから、「あれ?こんなんだった?」って感じだけど、まあいいや。
注:会話文は訛ってます。お気をつけ下さい。
その1 どこからか竹を取ってくる
母:今年はシンメイサマ(うちの隣の祠)のとこのが大きくなったから、わるさと(わざと)切らねーでおいてよかった。
竹やぶまで取りにいくんじゃコトだかんな。
私:それってうちの竹なの?
母:元はうちのさ。じんじんに(順々に、じょじょに)隣に行っちゃったんさ。
その2 物置から骨組みの棒を持ってくる
その3 骨組みを組み立てる



これが一番の難関。先祖代々伝わる骨組みで、はめ込み式になっている。
叔母:これが前かね?
母:書いてあるべ?
私:書いてある!「前北」だからこれでいいんじゃん?
母:ほれ、ちゃんと、おさまえてろいな。
私:押さえてるよ。あ、あぶない!上のが落ちるよ。
叔母:あっちがいいと、こっちが外れるで毎年大変なんだよ。
私:下を全部はめてから上をやったほうがいいんじゃん。
母:これはどこだ?
叔母:「後西」だからこっちでいいんだよ。
私:下のは、刺さるところが細くなってないと、穴に入んないからこれじゃないよ。
母:去年、印、付けといたんじゃなかったっけか?
叔母:付けたけど、いら(たくさん)書いてあって分かんなくなっちゃうんだよ。
母:お前、分かるように書いとけ。
私:もう大丈夫だよ、できるって。
母:出来上がると、毎年、そう思うけど、バラバラにすると結構分かんねえもんだぞ。
私:大丈夫だって。(←けっこうナメてる)
その4 板をはめゴザを敷く


3枚の板をはめる。
その上にゴザを敷く。
母:本当は毎年、新しいゴザを買うんだけどな、まぁいいやナ。
その5 ワケのわからん掛け軸をたくさん吊るす
位牌の紙版みたいな掛け軸がたくさんあるのでそれを上の横木に掛ける。
私:これ順番とかあんの?
叔母:なんでもいいよ。
母:あんまり古い人のは掛けなくていいや。
私:そんなんでいいんだ。
叔母:あぁ、13仏は真ん中だよね。
母:そうそう、それだけあってれば適当でいいゾ。
その6 竹と笹を付ける

取ってきた竹を2本両脇の柱にくくりつけ、枝をまとめる。
前面の上と下の横木に沿って縄を渡す。
下は笹を付ける。
上は後でホオズキを付ける。これは多分明日用意するっぽい。
叔母:今年はやけにこじんまりしちゃったね。
私:え?どの辺が?
母:適当に竹を切ったら短すぎたんだよ。やっぱりちゃんと測んないとだめだな。
叔母:いつも天井まであるもんね。
私:そういえばそうだね。(今年は超テキトーだな)
その7 色紙を飾る




黄、白、赤、緑、紫のお寺っぽい色の色紙を重ねる。
ちなみにこの五色にはそれぞれ意味があるとか。白が大日如来で、とか。
交互に切れ込みをいれて、細い先っぽによりにをかけ、四隅に掛ける。
よくわからないけど、下のほうは手でもみくちゃにする。
私:これ、順番は?
叔母:いいんナ、何でも。
私:切り込みの幅って同じだっけ?
叔母:いいんナ、何でも。
私:いつもさ、下に行くほど広くなったんじゃなかった?
叔母:じゃあ、次から、そうしな。
私:……。
その8 位牌や仏具を並べる

普段は仏壇に入ってる1セットを出して並べる。
右上段から古い順に並べる。
ちょっと互い違いにしないと並びきらない。
真ん中上段は仏像。
母:左上から古い順な。
叔母:順番があるんかい?
母:あるんだと。新しい人のを上にしたら、おじいさんが「子は下だゾ」って言ってたよ。
私:おばあさんのは?
母:おばあさんは真ん中じゃないと、おじいさんが気を悪くすんべ。
私:(そういうもんか)
その9 これで出来上がり!
こんな感じでできあがり。
あとは明日の迎え盆にホオズキや茄子とキュウリの馬を用意したり、
水となんかの葉っぱを入れた皿とかを飾る。
母:本当は明日(8月13日)にやるんだけどさ、うらんち(おとなりさん)も前の日にやるっていうから
うちも今日やっちゃうことにしたんだ。
叔母:そうだよ。一日に全部やったらコトだもん。
私:なるほど。