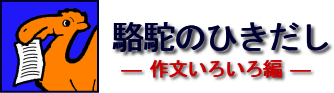
駱駝のひきだしから出てきた小学生のころの作文などを一挙公開!
駱駝の国語力を笑ってください。
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 3年1組のころ | 5ハウスJ組のころ | 中国文学科Aのころ | Yゼミのころ | D班的時候 | |
| ひるねねこ | デパート | 春はバスに乗って | 卒論の予告編 | 吐魯番的照片 | |
| 注意: 「吐魯番的照片」は中国語です。ブラウザのメニューバーの「表示」からエンコードを簡体字中国語に切り替えてご覧ください。 | |||||

ねこの気持ちがよくわかる駱駝ちゃんね。
かわいがっている様子がよくかけました。
(担任の秋池先生)
3年1組 だーだお らくだ
うちの庭のすみに古いいすがあります。
そのいすの上でいつもひるねをしているねこがいます。
ときどき見にくると、5ひきぐらいでかたまっています。
きげんが悪いときは、つめをたてて、いまにもとびつくようなかっこうをします。
でも、わたしはそんなのかまわないで、
「ニャーオ。」
と鳴きまねをしながら、ねこのあたまをなでてきげんをなおします。
そうすると、
「ニャー。」
とねこは、かわいらしい鳴き声で鳴きます。
それから、わたしはねこの首を、なでると、ねこは気持ちよさそうに目をつぶって、
「ニャア。」
と鳴きました。
そのねこをわざと家の中にいれてやりました。
ねこはカーペットの上までくるとあおむけになって、右をむいて、
「ニャーオ。」
こんどは、左をむいて、
「ニャーオ。」
と鳴きました。
きっとカーペットがふわふわしているから、じゃれたのだとわかるけど、
そこで、ずっとまるまってうごかなかったので、さきに二階にいって、ねこがあがってくるのをまっていました。
少したって見てみると階だんを半分ぐらいのぼっていました。
また少したって見てみると、もう階だんを一だんのぼると二階というところまできていました。
またまた、少したって見ると、もう、へやの入口まできていました。
そして、おもしろいことにきがつきました。
それは、ねこをこたつの中に入れていっしょにもぐってあそぶということです。
そのとおりねこをこたつの中に入れたけど、まっくらの中にねこの目だけがひかっていて、こわいからやめました。
わたしは、『そのねこが、あしたも、あさっても、しんあさってもそのねこがいればいいなぁ。』と思いました。
だめだよね、家の中に野良猫入れちゃ。しかもこたつにまでさ。この作文の一番の笑いどころは「なでる」を「なぜる」と書いて先生に赤で直されているところ。それと、この作文ファイルを通して言えるんだけど、最後の一文のように、主部を繰り返すクセがある。「わたしは」と最初に書いておきながら、また文末に「とわたしはおもいました」がくる。ちゃんと推敲しようよ。
デパート
(夢の話 第1夜)
そのとき私は駅ビルの中にいた。どこの駅で、何という名のビルであったか、などということは知らない。というより、あえて知ろうとする必要がないのだ。自分のおかれた舞台設定に、何の疑問も持たずにストーリーは始まる、それが夢の世界の常識である。だから私と数人の友人たちは何の前触れもなくそこにいた。
その建物はまだ新築とみえて、真っ白い蛍光燈がこざっぱりとした店内を明るく照らしだしていた。私たちはそこを昔から知っていた場所であるかのように歩いていた。
私たちは一階の食品サンプルを並べている小さな店に入った。私たちのほとんどは、この店で何か買い物をする目的があったわけでなく、いわば付き添いで来たらしい。買うつもりのない商品を二、三人に分かれてあれこれ批評していると、友人Aが、
「○○ちゃんねぇ、買うもの決まったって。」
と言いながら寄ってきた。一人が会計をしている間、私たちはビルの出口がわからなくなったことに気付いた。一人が会計の若い店員に尋ねた。
「すみませんが、このビルから出るにはどっちに行ったらいいんですか?」
「あちらですよ。」
と、その女性は手全体で示した。礼を言い、言われたとおりに通路の行った。すると奇妙なことに、業務員用らしき狭い階段にでた。ここは一階である。建物から出るのに何故、階段それも上りしかない階段を使わなければならないのか。そんな不安にかられながらもしかたなしに階段を上って行った。
二階に着くとさっきとは、うって変わった古めかしいデパートの一角にでた。くたびれた蛍光燈がごった返す店内を薄暗く映しだしていた。このデパートを奥へ奥へと進んで行くと、途中で変に曲がりくねっていたり、段や傾斜がついていたりと、へたをしたら迷ってしまいそうな造りである。どうやらこの建物、増築に増築をかさねてきたのだろう。それにしても奇妙な造りである。
さらに歩いてたどり着いたところは、また別の階段であった。デパートの階段というものは、たいてい薄暗いものである。この階段もそうであった。しかし、先ほどの階段と違って、今回のは広く、下りもあった。そこから少し離れたところには、さっきの真新しい駅ビルとの境目がある。設計ミスなのか、新築したほうが少し低いために旧館のほうに軽い傾斜が1メートルぐらいの距離でついていた。
そんなことはさておき、私たちが探しているのは出口である。紺の作業服に水色の三角巾といういでたちで階段の掃除をしていた中年の女性に尋ねた。すると、その女性が教えてくれたのは、出口のことではなく、こんなことであった。
「この通路をまっすぐ行くと洋服売場にでるの、そうしたら最初の十字路の右のつきあたりをみてごらんなさい。でも通りすがりにチラッとだけよ。見たことがばれたら大変なことになるから。それともう一つ、その十字路にでる途中に大きな鏡があって、その鏡から映った本人そっくりな人間が出てくるの。どういうわけか、その出てきた人間は、さっき言った十字路のつきあたりの部屋に行きたがるの。それを絶対、止めなきゃだめよ。
それを聞いた私たちは一般の買い物客から、命をかけた通路探検隊になっていた。
十字路のつきあたりには何があるのか。見てはいけない何があるのか。何にせよ、良からぬおぞましいことが、そこに秘められているに違いない。あまり楽しくない想像をしながら歩いて行くと、いつの間にか大きな鏡の前にさしかかっていた。
鏡を横目で見ながら、皆、体中が緊張しているにもかかわらず平静を装って黙ってぎこちなく歩きだす。誰が言ったわけでもないが、心にすきがあれば今にも鏡の向こうの自分が勝手に動きだしそうに思えた。あの人は、ただ映った本人にそっくりな人間が出てくると、としか言わなかったが、このまま頭のてっぺんから足の先まで神経の塊となっていけば、うまくいきそうに思えた。私はそう信じていた。気分は大いなる謎の門を通り抜けるアトレーユであった。
しかし、所詮、私たちはバスチアンであって勇者アトレーユの器にはほど遠いようだ。私たちのひそかな努力をあざ笑うかのように彼等は動きだした――驚きと恐怖で凍り付いた私たちを見捨てて。
ただただ見つめるばかりの私たちをよそに、鏡は限りなく静かな水面と化し、そこに小さな点ができるやいなや波紋が広がった。水面が盛り上がると、そこを突き破って滑らかに指先が、腕が、頭が、足が、体が次々と出てくる。それはあっという間の出来事であったのだが、何故かスローモーションを思わせる画像であった。
あっけにとられていた私たちは、すぐさま我にかえった。いや、かえされた、と言ったほうが的確かもしれない。出てきた模造人間たちが、いきなり走りだしたのだ、例の部屋、目がけて。何かに取り付かれたように駆けていく自分のコピーを私たちは無我夢中で捕まえた。腕を相手の体に巻きつけてひきずられながらも必死にくい止める姿はまるでアメフトのようである。それも捕まえている側と逃れようとしている側の人間がそっくりなのだから、はたから見たら何と滑稽な様子であろう。
しかし当人たちは、とにかく必死なのである。相手が自分のコピーならば、力も自分と同じ筈、正反対の方向に同じ力で引っ張り合えば、当然どちらにも動かない、つまり止まるということだ。

バランスを崩してバタバタと、だきついたままの状態で床に倒れ込む。自分が相手をおさえきれたことにほっとして顔をそっと上げると、皆もどうやら同じようにあちこちでうずくまっていた。が、前方を見てハッと息を飲んだ。フロアーに響きわたる足音と共に友人Hが、ズルズルと引きずられながら十字路の角に消えていく。皆も気が付いて、いっせいに起き上がって追いかける。しかし、追いつくには距離がありすぎた。私たちが十字路までくると、友人Hがつきあたりの部屋に引きずり込まれるところだった。もう、間に合わないことを悟った私たちは黙って彼女を見送った。
部屋に入っていく人間を見るということは同時に部屋の中をかいま見てしまうということでもある。このことに全く気付かなかった私たちは見てしまった。チラッとではあったが、、出入口のそばを白い作業着に白い長靴をはいた男が、いくつもの肉の塊をぶらさげたキャスター付きの鉄竿を押して横切るのを見てしまったのだ。
それを見てはじめて『見たことがばれたら大変なことになる』というあの言葉を思い出した。今から「あっしらはどこにでもいる普通の買い物客ですぜ、何にも見やせんでしたよ」なんてわけにはいかない。かくなるうえは逃げるのみ。一瞬のうちにそう考えた私たちは、ぐるりときびすを返して一目散に逃げだした。
ところで例のコピーたちであるが、以後どうなったのだろう。通路の床の上に置去りにしたままで後に登場することはなかったが、きっと消えてしまったか、鏡にもどったといったところだろう。
例の部屋を背に全力で通路を走った。途中でふりむくと、まるでマフィア映画から抜けだしてきたような男たちが拳銃を片手に追ってくる。信じたくないが信じざるをえない状況に頭は混乱し、ただただ逃げることしかできなかった。しかし、逃げようにも、デパートの中である。すぐに通路のつきあたりが間近になった。正面の壁には大きな窓が並んでおり、南向きなのか日の光がいっぱいに入り込み、白い壁や床をいっそう白く浮かびあがらせていた。窓から見える風景はどう見ても四、五階からのものであった。
そこは通路より少し広くなっていて右側はすぐ壁だが左側は壁ではなかった。階段であった。広くはなかったが明るく、清潔な感じがする階段が下に続いていた。
私たちはその階段をめいいっぱい駆け下りた。てすりごしに下をのぞくと階段が長方形に渦を巻きながら幾重にもかさなっていて下に吸い込まれそうである。踊り場で右に折れ向きを変えて駆け下りる、それを幾度となくくり返し、3階分ほど下りてきたときである、私たちのけたたましい足音をかき消すかのように、よりけたたましくそれでいて不気味な靴音が頭上で響いた。
私たちは考えた。この階段をひたすら下りていったとしてもいつかは追いつかれてしまうだろう。かといって途中の階に出られる通路はなく、ただぐるぐると下に続く階段なのである。助かる方法は一つ、どこかに身を隠し、相手をやりすごし、階段を引き返し、さっきの洋服売場に行き、人ごみにまぎれ、なんとかこの建物から脱出するのだ。
ここまではよかった。いざ、実行するとなると、そううまくはいかない。隠れる場所など見当たらなかった。いちかばちかの賭けにでた。
このあたりが今考えれば実に馬鹿げている。私たちは踊り場のてすりを乗り越え、てすりを支えている縦棒につかまってぶら下がったのだ。くり返し言うようだが、本人たちは本気なのである。確かに私たちがぶら下がっている目の前の踊り場からは、棒につかまっている握りこぶししか見えないわけだから、うまくやり過ごすこともできよう。だが、反対側の踊り場、つまり半階分高い向かいの踊り場からは、この上なくよく見えるのは必然のことであろう。
案の定、追っ手は私たちに気付き、向かい側の踊り場で足を止めた。そして顔を見合わせニヤッと笑うと無言のまま、銃のねらいを定めた。私たちは、もはやこれまで、と目をギュッとつむり、顔そむけた。映画の音響効果そのままの銃声がたてつづけに耳をついた。そむけた顔の反対側の首のつけ根を銃弾がかすった。自分が傷みを感じている姿は見えたが、実際に傷みは感じていなかったように思う。
彼らの腕が悪いのか、それとも目の前で身動きのとれない標的を少しばかりからかってみたくなったのか、幸いその程度で銃声は途絶えた。まるでテレビの画面を見ていたかのような私の視野は、また元の私の目から見た視野に切り替わった。
カツッ、カツッとすぐそばで二度、足音が聞こえた。頭上の床を見上げると、そこにはあの部屋に引きずり込まれたはずの友人Hが微笑んで立っていた。
「さぁ、早く!」
と、彼女は手をさしのべた。私たちは思いもよらない救世主の出現に、喜びと驚きが感情の50%ずつを占め、微妙な笑顔でうなづいた。
そのとき私は布団の中にいた。
これは課題でもなんでもなく、趣味で書きとめていた夢の話。文芸部でもないのにね。で、友達に無理やり読ませていた。読まされたほうはさぞ迷惑だったろうね。いまもそうだけど、回りくどい描写のわりに内容がくだらないよね。すんません。
そういや、出始めのしょぼいワープロで打っているので、蛍光灯の「灯」の字が旧字体しか出なかったのを覚えている。あと、直前にきっと「はてしない物語」を読んだんだろうね。だから、アトレーユとか出て来る。恥ずかしいな。笑ってください。
この頃は、変な夢をたくさん見ていた。自分が死んでいるのに肉体が腐るまで生活できる夢とか、雪山で遭難した少年を助けるレスキュー隊の夢とか。今でもけっこう変なの見るけど、覚えていないよなぁ。
春はバスに乗って
国語表現法・課題「小説」
金曜2限 中文A 駱駝
K駅を出ると、いつもより高い位置から自分を照らす太陽に目を細めた。女子高へと続く行列からはじけ飛ぶ笑い声も、代書屋のアルバイターが張り上げる客引きの声も、今日は聞こえない。駅を目指してせわしなく足を進める人々も見当たらない。張りつめた空気を黄色い光線が溶かしてしまったようだ。銀行の花壇の前のバス停にも日が当って、狭い駅前少しだけ広く見える。「一限休講」の思わぬ効果に新鮮さを感じながら、横断歩道を大股で渡ると、前を行く小柄な老婆の姿が目に入った。

小さな巾着袋を握り締めた左腕は長年使い込んで折れ曲がった腰を励ますべく、しっかりと添えられている。右手につかんだ杖の柄に昔よりはずいぶん減ったであろう体重をかけ、草履の底を地面に擦りつけながら、少しずつ、少しずつ、左右の足を交互に移動させている。何だか追い抜いてしまうのがためらわれ、速度を心持ち緩めた。
バス停に着いたときには白髪を包み込んでいる黒い毛糸の帽子がかなり間近に迫っていた。不意に帽子が起き上がると、今度は背中をめいいっぱい反らせ、時刻表を指でなぞりながら顔だけ前に突き出している。すぐ脇に立った私に時刻表を指差して言った。「次は28分ですかねえ。」張りのある母音を強調した高い声だ。「いや、これは休日だから、13分の松山行きがあるはずですよ、えっと、ここに。」透明なプラスチック版の上を、二本の対照的な人差し指が動く。
「あと何分ぐれぇですか。」皺だらけの顔の下半分を必要以上に動かし、黒目ばかりの小さな瞳のまわりの皺を微笑ませて首をかしげて聞いてきた。「15分ぐらいですね、遅れていなければ。」となりに並んで、時計をちらっと見て、口元で笑顔を作りながら私は答えた。「そ、ですか。」と言うと、後ろを確認して、その場にゆっくりとしゃがみこんだ。杖の下のほうにつかまり、照れくさそうな表情で見上げて、続けた。「いやぁ、歳とると、目は見(め)ぇなくなぁる、腰は痛くなぁるで、どぉしょもねくて……。」卑屈さのない、明るい声だった。日なたがよく似合う笑顔だった。それに感化されて、自然と私の顔にも笑みが浮かんだ。
商店が並ぶ駅前通りのずっと先のゆるやかな坂の頂上から豆粒のようなバスの正面が現れる度に「あれですかねぇ。」「うーん、どうでしょう……。」と、目を凝らしてみるが、なかなかお目当ての行き先を書いたバスは顔を見せない。ほかの路線ばかりが目の前を通り過ぎ、新しい客を乗せて、もと来た道を戻っていく。ここが始発でないこの路線バスは大抵遅れる。いつものことだ、仕方がないことと諦めているが、その分運賃を値下げしてほしいとも思う。
やっとバスが来た。結局、5分遅れだ。いつの間にか、後ろに7、8人の人が並んでいた。オレンジ色の車体の後ろのドアがちょうど先頭の老婆の前で、プシューッと音をたてて開いた。「ヨイコラセットッ。」ゆっくりとステップを上がる老婆の足元を気にしながら、後に続いて乗り込む。西へ西へと走るので日向を避けて右側に座り、整理券を定期入れに入れる。あとは終点までの30分あまり、流れて行く景色を見ていればよい。
K市からY町を抜けてH市に着くまでに景色は市街地と田園地帯をくりかえす。なかでも私が一番気に入っているのが、荒川の広い河川敷。今日も黄色い土手が見えてきた。日差しを溜めて暖かくなった車内にまで満開の菜の花が放つ湿った土と草の匂いがした。
カーッ!こっぱずかしい!題名はいわずと知れた「春は馬車に乗って(横光利一)」のパクリだし。文の感じも高校のころと進歩なし。述語までが長すぎる。ちなみに広外の写作(作文)の課題でも、ネタに困ってこの話を書いた。でも中国語で長い文章書けないから、超簡潔。でもそのほうが結果的にすっきりしていていいかも。
もう卒論を書かずにはいられない!
予告「曽侯乙墓の文字資料」
殳とは如何なるものか?〜曽侯乙墓における新事実〜
君は「殳」という字が読めるだろうか?
辞書を引かずに正しく読めたら10点あげよう(Y先生のマネ)。
音はシュである。そして意味は...「つえぼこ」と、いう。
ツエボコという音が何となくカマボコを連想させて2分間は笑えるが、さらに続くその説明が変だ。
『8本のささらを有し、竹でつくられる。刃はなく、兵車の上から敵を遠ざけるのに用いる』らしい。
「つえぼこ」が即ち「杖矛」で、昔の武器であることはわかるのだが、ささらというのがわからない。
しかも馬車の上でふりまわすだけの棒なのに8本もついているとは...。
ハルチ女史によると、「ささら」とは『お鍋についたコゲを落とすやつ』だそうだ。
小さな竹箒の先のような形をしている。
それが3mもある長い柄の先に8本もついているのだという。
想像だに謎めいた武器である。
もし一度だけ古代にタイムスリップできるとしたら、私は迷うことなく、この「殳」をふって懸命に戦う雄姿を見に行こうと思う。
辞書に載っている「殳」の図はまちまちで、「刃が無い」って言ってるのにどう見ても刃がついているものや、先が箒のようになっているものなど、どれも信用できない。
これらの解釈は、どうも≪説文≫や≪左伝≫の注から想像して書いたものらしいが、その注自体が、先が8角形だの何だのとマチマチなことを言っているのだから、らちがあかない。
とにかくこの、先秦時代の武器は漢代の人でもよく分からないという、かなり旧式のシロモノらしい。
加えて木製だと耐久性が悪いので現存する確率も低い。
何とミステリアスな武器であろう!
こんな研究心をくすぐるものがかつてあっただろうか!
その「殳」が、何と曽侯乙墓から出土した!!
それもこれまでの定説を覆す逆転ホームランだ!!
青銅製の「殳」という文字が鋳込まれたこの出土物が、今2000年の謎を解き明かす!!
乞うご期待!
レポート用紙の端切れに上のような文が書いてあったのを最近発見。当時、卒論書くのが辛くて、ちょっと自分を励ますために書いたらしい。かなり意味不明。当時、私たちの学部の卒論は「ワープロ不可、すべて指定の原稿用紙にペン書きのこと」という腱鞘炎コースまっしぐらなルールがあったんですな。そもそも、私のやっていたことはワープロで出ない字がてんこ盛りだったんで、手書きしかないんだけどね。ちなみに「曽侯乙墓」は編鐘が完全な状態で出土したことで有名なお墓です。